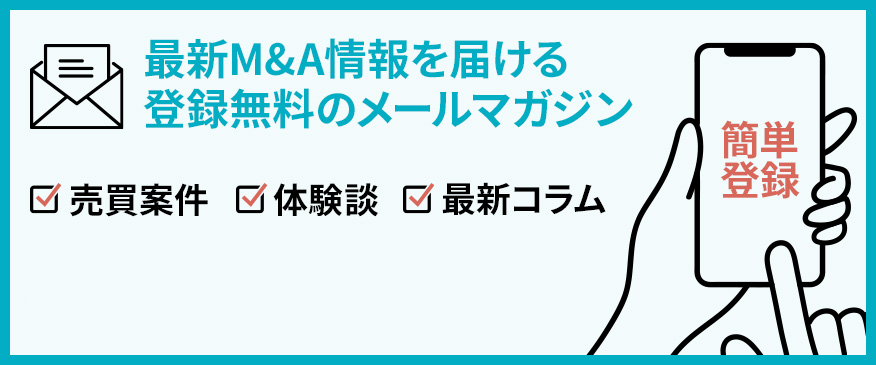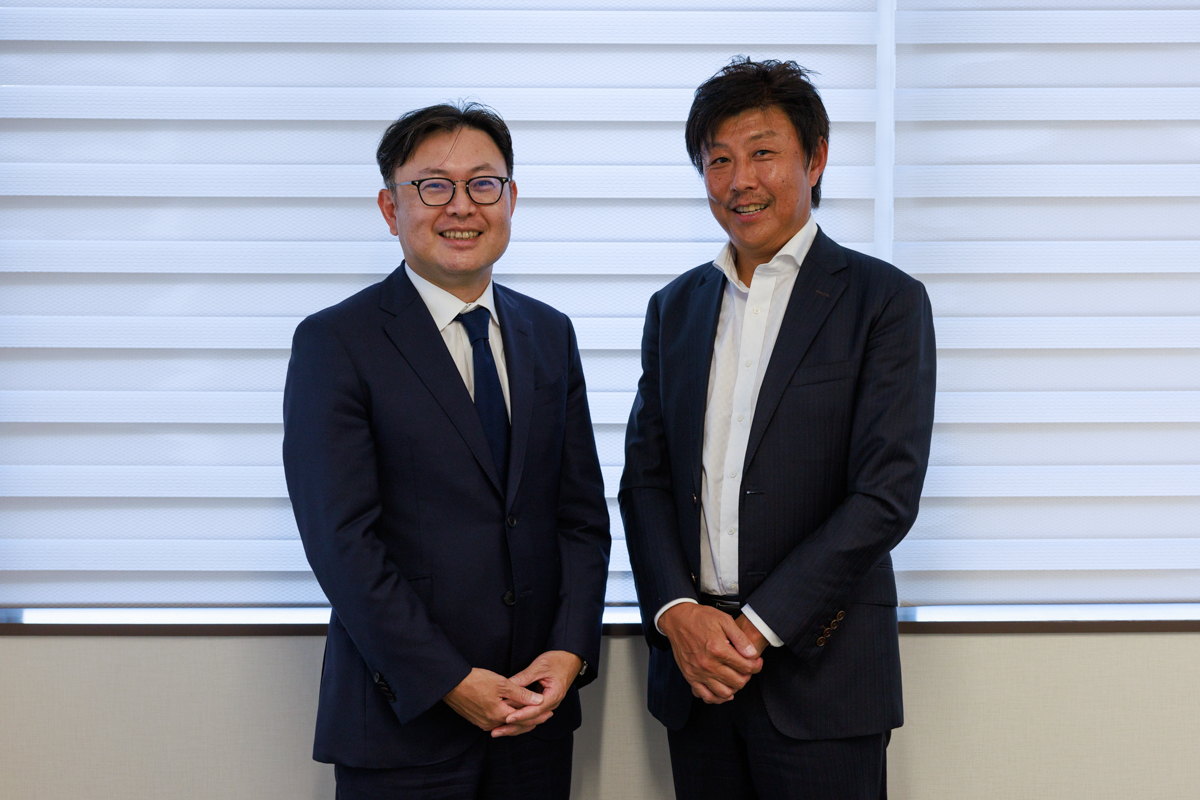ローカルM&Aマガジン
日本の経営者には、高齢化により次世代への事業承継が常に問題として付きまといます。
しかし事業承継を検討しても、後継者がいないことと借金が多額で後継者に引き継げないことが最大の課題となります。
今回の記事では、後継者不在の救いの一手となりうる「事業承継型M&A」と借金を後継者に残せないときにスポンサーに引継ぐ「事業再生型M&A」について解説します。
「事業承継型M&A」とは?

事業承継型M&Aとは、M&Aを活用して事業承継すること。代表的なM&Aです。
経営者が会社売却を決める理由の大半は、後継者不在です。後継者不足が顕著な現代の日本において、事業承継型M&Aを選択する企業が増えているのです。
代表的なスキームは株式譲渡や事業譲渡です。後継者がいない株主兼オーナー経営者が第3者に事業承継を目的に実行するM&Aです。
▼事業承継型M&Aの成功事例として、「妥協することなし! 大満足のM&Aを実現した体験談」のコラムもぜひご覧ください。
「事業再生型M&A」とは?

事業再生型M&Aとは、債務超過などで企業再生の必要がある場合に、スポンサーに会社を引き継いでもらう際にM&Aを活用する手段です。再生の肝となるのは借入金をスポンサーからの譲渡代金で返済できるか、また、不足する場合は金融機関から債権カットしてもらえるかどうかにかかっています。
現在、日本企業の約99%が中小企業で、そのうち約70%が赤字だといわれています。
経営破綻すれば最終的には倒産という事態に行きつきますが、するとそこで働く従業員は路頭に迷うことになってしまいます。
そんな最悪の状況に陥る前に、金融機関に支援してもらいながら事業再生を図る手段が、事業再生型M&Aなのです。
▼事業再生型M&Aの成功事例として、「【介護事業者】M&A体験談①」のコラムもご覧ください。
事業再生型M&Aにはさまざまなスキームがある!

事業再生型M&Aを成立させるには、主に次のスキームが用いられます。
私的整理を利用!
事業再生を試みる会社の主目的は、事業を存続させ、従業員の雇用を守ること。そこで、まずは私的整理で金融機関の大口債権者に協力してもらい、再生を図るという方法が考えられます。これは法的整理(裁判所へ申し立ての必要のあるもの)ではなく、私的に金融機関と交渉し、支援をもらいながら、スポンサーを探し、事業を存続させるスキームです。
ここで大事なポイントとなるのが、資金繰りです。金融機関と交渉して、スポンサーに引き渡すまでの期間、自力で運転資金がもつかということです。
また、金融機関が事業再生の協力をしてくれるかということも大事なポイントです。それは何かというと、スポンサーからの譲渡代金<借入金の場合です。譲渡代金>借入金であれば問題ないのですが、借入金が残った場合、その分の債権放棄してくれるかということも重要となります。
金融機関にとって貸金の一部を放棄(カットすること)するのは簡単ではありません。その事業の公共性や破綻した場合の社会的影響力と再生プロセスやカットする金額などが総合的に判断されます。だから、どの企業も私的整理に応じてもらえるわけではありませんので、悪しからず、ご了承ください。
「会社分割」を実施!
事業再生の手段として会社分割を利用することもあります。会社分割とは、会社の一部の事業を切り離して会社を二つに分けることです。清算する部分と再生する事業を分ける際に会社分割も利用します。
会社分割は、お客様や取引先、社員と締結する個別の雇用契約などに、資産や負債、就業規則まで包括的に移転させることができるため、事業譲渡と比較した場合、契約が引き継がれるというメリットがあります。
▼会社分割については、「会社分割という選択肢――メリットとデメリットを解説」でも紹介しているので、参考にしてください。
事業再生型M&Aには、経営者の覚悟が必要!

会社を維持・再建できる事業再生型M&Aは、経済産業省などから発表されている「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」でも公開されています。中小企業者の維持・発展や事業再生等を後押しし、日本経済・地域経済の活性化を図るという狙いがうかがえます。
会社が経営破綻したら、最後の手段として破産手続きがありますが、その一歩手前が民事再生や会社更生、そしてその一つ手前の手段として挙げられるのが私的整理の活用です。いずれも、スポンサーを探して事業を譲り受けて、再生の道を探るのです。これが事業再生型M&Aです。
実際、事業再生M&Aで事業を譲渡できて、債務がきれいになったとしても、経営者の手元には多額のキャッシュが残るわけではありません。金融機関の保証債務を外してもらう拠り所は国が出している「経営者保証ガイドライン」です。自分の資産を全て、債務の返済に出して、生活に必要な資産は所有が認められるようです。
そのため事業再生型M&Aにおいては、経営者は「肉を切らせて骨をたつ」くらいの覚悟が必要といえます。
まとめ
以上のように、「事業承継型M&A」と「事業再生型M&A」は後継者不足や借入金にあえぐ、日本の多くの中小企業の永続する手段となり得ます。
いずれのタイプのM&Aを選択するにせよ、大切なのは事業の魅力を最大限に高めることです。
たとえ、債務があったとしても買い手となる企業が「投資する価値がある」と魅力を感じる会社になっていること、これが重要です。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役