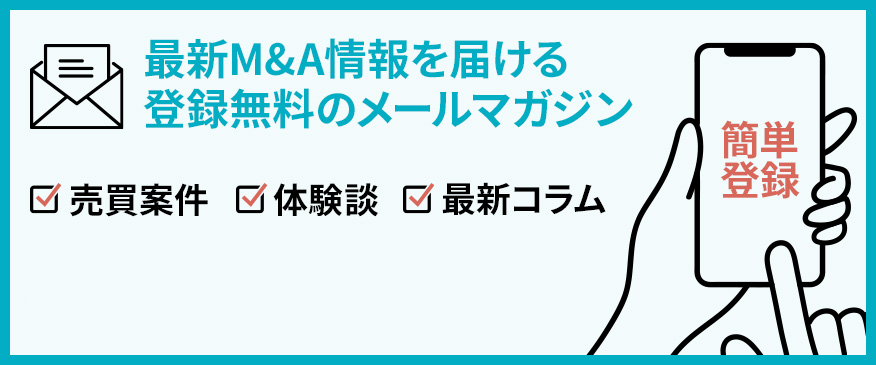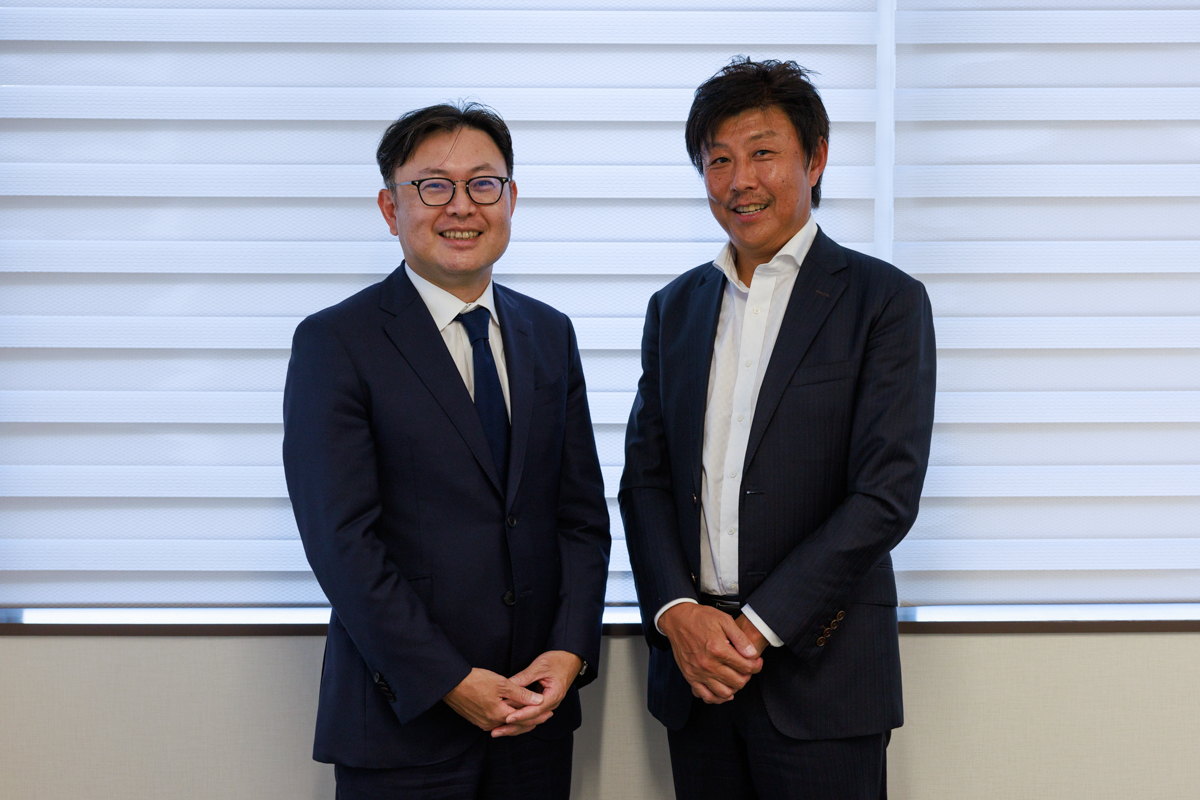ローカルM&Aマガジン
(質問者様)
2店舗を展開する、食品スーパーマーケットの経営者です。
70歳を過ぎてそろそろ引退しようと考えていますが、跡継ぎもいないし、コンビニやドラッグストア、ネットスーパーにおされて最近の売上はジリジリと右肩下がりの状況なので、会社をたたむことにしようかな、と……。手続きや費用、注意点などを教えていただきたく、相談に来ました。

(小川)
会社解散・清算の手続きをして会社を廃業する、ということですね。
その場合、事務的な届出に進む前に、関係者に対する説明が必要です。従業員や取引先、金融機関などですね。
ただし、単に「廃業します」というのではなく、従業員にいつまで給与を支払うのか、借り入れの残高返済はどうするのかなど、実際的な話を詰めなければいけません。
加入している地域の商工会や組合からの脱会、法人で契約する保険の解約などもやっておきましょう。
(質問者様)
40年間、小売の世界でやってきて関係先はたくさんありますから、話を通すだけでも結構な手間ですね。法的に必要な事務処理は、どのようなものがあるのでしょうか?
(小川)
まず、取締役会と株主総会での決議です。解散決議は普通決議ではなく特別決議で行なわなければいけません。
質問者様の会社の株主構成と取締役の構成はどうなっていますか?
(質問者様)
取締役は私と妻だけで、株主も同様です。
(小川)
それならシンプルですね。続いて、清算人の選任が必要になります。会社清算の作業にあたる法的な担当者ですね。
清算人は、定款や株主総会で特別に定められない限りは取締役が選任されます。質問者様の場合は奥様と二人で清算人になられて社長様が代表清算人になる、という流れです。
ここまでが完了したら、2週間以内に解散登記と清算人登記を行なわなければいけません。2週間が過ぎて解散登記がなされないと法人税の納付義務が生じてしまうので注意しましょう。
登記が完了したら「異動届出書」と「登記事項証明書」を作成し、解散のための処理が必要な各公的機関に届出を出します。会社の状況によって求められる書類が違ってくるのと、書類によって税務署への提出だったり都道府県税事務所への提出だったりと役所が違ってくるので、事前にしっかり調べてから準備してください。
ほか、社会保険や雇用保険などの喪失届関係も提出が必要になります。届出関連はとても煩雑なので、税理士や行政書士、社会保険労務士などに協力を依頼したほうがいいかもしれません。
(質問者様)
やることがたくさんありますね……。
(小川)
残念ながら、まだあります。
会社をたたむ場合、債権者がいる場合は申し出るよう、官報に公告を出さないといけません。2ヶ月は申し出の期間を設けます。
そして、決算書類の作成です。事業年度の開始日から解散日までの決算書を作成し、会社に残る資産と債務を確定させます。解散日から2ヶ月以内に確定申告を行ない、法人税を納付します。
そうしたら、金融機関などの債権者に債務を返済し、残った残余財産を株主、今回は社長様と奥様に持ち株比率に応じて配分します。非上場企業の株式や不動産などは換金しづらい場合があるので、専門家のサポートを借りて時間をかけて残余資産を整理することになります。
ここまで完了したら、最終の決算報告書の作成と株式総会における承認、そして法務局で清算結了の登記を届出して、会社をたたむ処理は終了となります。

(質問者様)
なるほど。思った以上に事務が多くて驚きました。ところで、こうしたプロセスに費用ってどれくらいかかるものなのでしょうか?
(小川)
従業員には会社都合で辞めてもらうことになるため、規定になくても退職金を出したり、特別手当を出したりする会社が多いですね。
事務的な費用でいうと、官報公告が10行で3万6000円、登記を何回かすることになるので、司法書士に頼むと10万〜15万円が登記の回数分かかります。ほかに、税理士に払う決算報酬もありますね。
それから、売却が難しい機械や設備については廃棄しないといけないので、撤去費用がかかる場合があります。さらに拠点が賃貸の場合は原状回復の費用もかかってきます。
(質問者様)
費用もけっこうかかるのですね。うちは小売で店舗の土地を借りているので、きれいにして返すとなると、相当お金がいるかもしれません。会社をたたむのも大変なんですね……。
(小川)
ただし、国や都道府県の補助金が使える可能性があります。
タイミングや自治体によるのですが、新型コロナウイルスにより廃業を余儀なくされた会社への補助金や、廃業後に再度起業する場合の補助金、廃業後に経済的に困窮してしまった人に対する家賃支援の制度などが事例としてあります。
あとは事業承継・引継ぎ補助金がありますが、これは事業承継や統合などによる廃業を対象にしており、ただ廃業したいだけの場合には適用されません。
(質問者様)
廃業といっても、かなりハードルは高そうですね。ちょっと軽く考えていたかもしれません。
とはいえ、会社を継いでもらうアテがあるわけでもなし……。
(小川)
思い当たる範囲に後継者候補がいないのであれば、M&Aによって第三者に事業を引き継ぐという選択肢もあります。
業績が良かったり財産があったりする会社であれば、創業者が創業者利益を得られる場合もありますし、業績が下降気味で借金があっても、事業に魅力があれば、「再生型M&A」といって、金融機関と債務返済について調整しながらM&Aが実現するケースもあるんですよ。メリットは大きいはずです。
「うちを買ってくれる企業なんかない」と最初から諦めてしまう経営者は多いのですが、一度、M&Aの専門会社に相談してみると道が開けるかもしれません。
(▼関連コラム)
(質問者様)
ありがとうございます。M&Aという選択肢は考えていませんでしたが、経営の安定した他社に会社を買ってもらえて事業が続くのであれば、こんなに嬉しいことはありません。
自社をどうするか、もういちど真剣に検討してみます。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役