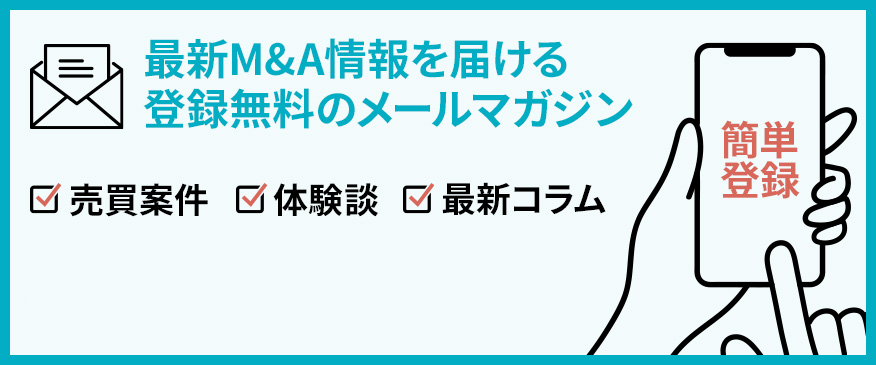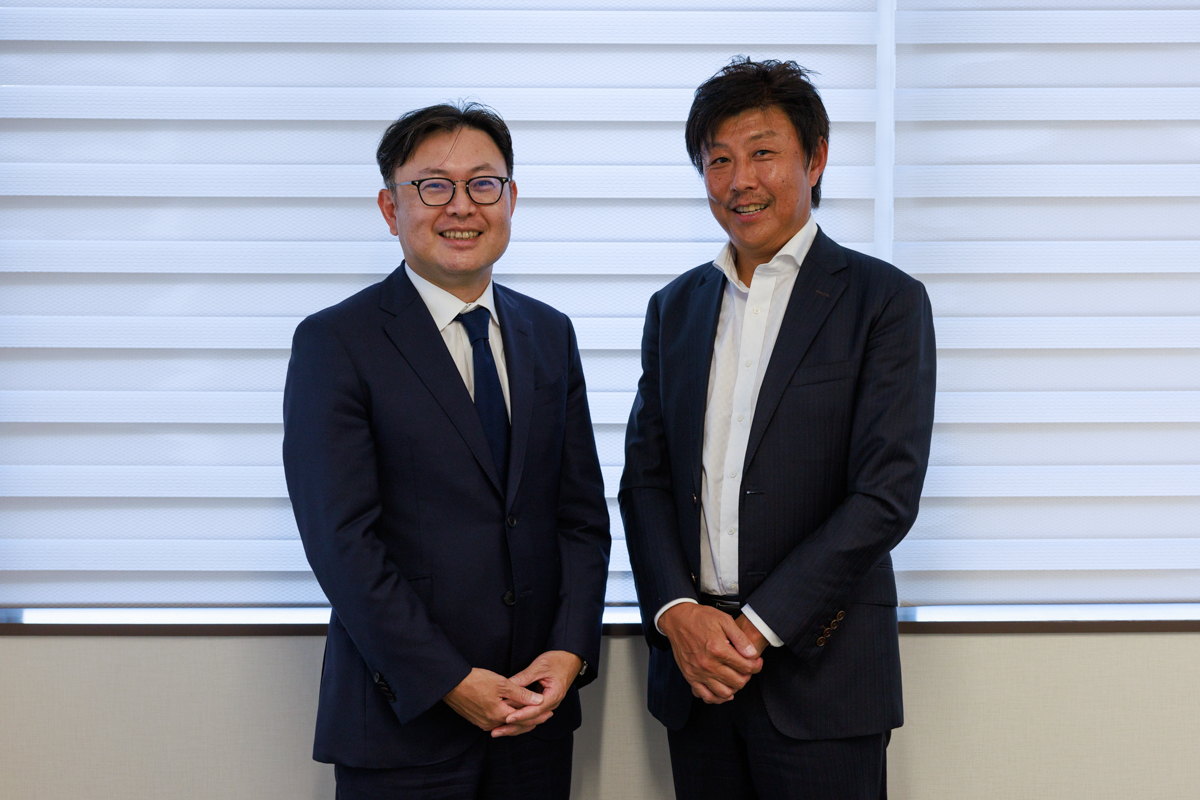ローカルM&Aマガジン
ただし、このコロナ融資が一つの要因となって、倒産する企業が相次いでいます。
今回の記事では、M&Aにまつわる失敗事例として、コロナ融資と資金繰りの関係について解説します。
コロナ融資とは?

コロナ融資とは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業活動に影響を受けるような中小企業を支援する目的で開始された融資制度です。
日本政策金融公庫や民間の金融機関が主導となって融資を行なった、国をあげての政策でした。
コロナ融資によるM&Aの落とし穴!
昨今、コロナ融資でお金を借りた企業経営者から「返済ができない、会社を売りたい。」という相談が増えています。そこでM&Aによる事業再生を期待するものの、M&Aは万能薬ではありません。
「借金の返済ができそうにないから、会社を売ろう。」という前に、自社の借金と営業利益、そして、毎月の資金繰りを見比べて、返済していけるものなのか、銀行にリスケをお願いして、当面の資金確保のために毎月の返済を止めてもらわないといけないのか。まずはこれを見極めることが肝要です。
資金繰りに詰まったら、お金を借りて凌ぐ、その延長線上にこのコロナ融資がありました。コロナのせいで売上が下降し、お金がない。コロナが収まるまでなんとかお金を確保しよう、これがコロナ融資の目的でした。
しかし、コロナのせいで売上が下がったのか、そもそも事業がよくなくて、売上が下がったのか、見極めることはされず、スピード重視がコロナ融資の特性で、それが今、問題視されているのです。
コロナ融資でお金を借りたことの問題点はどのようなところにあったのでしょうか。
問題点その1:そもそもの業績の悪さ

コロナ融資の一番の問題点は、会社の業績がコロナ前から低迷していた企業があった点です。
コロナ融資の返済が開始されてから事業再生の相談に来る経営者の共通点は、融資を受ける前から業績が芳しくありませんでした。なぜそのようなことが起こったのでしょうか。
それはコロナ融資の審査基準が、コロナで業績が下がったという要因は絶対条件ではなかったためです。
コロナ融資の機会が訪れたことで、もともと業績で苦しんでいた企業の借金が膨らむこととなりました。コロナ融資の返済が困難で、事業再生の相談に来る経営者は全てこの例に該当しています。
▼事業再生については、「再生型M&Aとは? 普通のM&Aとの大きな違いを解説」でも紹介しているのでご参照ください。
問題点その2:適切な判断の欠如
多くの経営者は、コロナ融資で事業資金が手に入るチャンスとして、一つの救いと考え、借り入れに踏み切りました。
しかし、その後の返済が困難となり、会社の先行きが見えなくなったのです。さらに、判断の欠如の一例として、借りられる最大の金額を借りてしまった例が相次いでいます。
企業によって、借りられる最大の金額は異なりますが、そもそも売上が不安定な状態で、例えば6000万円といった多額のお金を借りてしまっているのです。
業績が良くない状況において、さらに数千万円規模の借金をしているため、事業再生どころではなく、資金繰りに詰まって、倒産を考える必要が出てきていると言えます。
問題点その3:政府の審査基準
コロナ融資は、通常の融資の審査とは異なり、売上が前年同月より下がっていることを基準としています。これは、コロナ禍の特殊性からくるもので、多くの企業が借り入れを受けやすくなりました。
具体的には、法人については15%以上の売上高が減少していることが審査基準となり、ただ業績が下がっている企業にも支払われたことが問題と言えます。もちろん創業から間もない企業やそもそも信用情報に傷がある企業などは借りることはできませんが、必ずしもコロナで業績が下がった企業ばかりではないのです。
このように一部制度の穴をついて、返済能力のない借りるべきではない企業が借りたことが資金繰りで窮地に陥る原因となりました。
早めの決断が重要!

このような事例からわかるのは、簡単に借金を重ねることが、必ずしも最善の選択ではないということです。経営者として、借金をする際には将来の返済計画を立て、リスクを考慮することが重要でしょう。
コロナ融資は一時的な延命措置となっただけで、それが長期的かつ根本的な解決策とはなりえませんでした。資金繰りが苦しくなった場合、早急に適切な対策を講じることが、会社の存続を考えるうえで不可欠です。
コロナ融資で借金が膨らんだ企業には、銀行もさらにお金を貸してくれることはありません。適切なタイミングで会社をたたむ決断も含め、冷静な判断が求められるでしょう。
まとめ
以上、コロナ融資と資金繰りの問題は一筋縄ではいかないことがわかったでしょう。
簡単に借金をすることは、将来のリスクを増大させる可能性があることを認識し、早急な対策を講じることが肝要です
企業の価値を見極め、迅速かつ適切な判断を下すことで、未来への道が開けるでしょう。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役