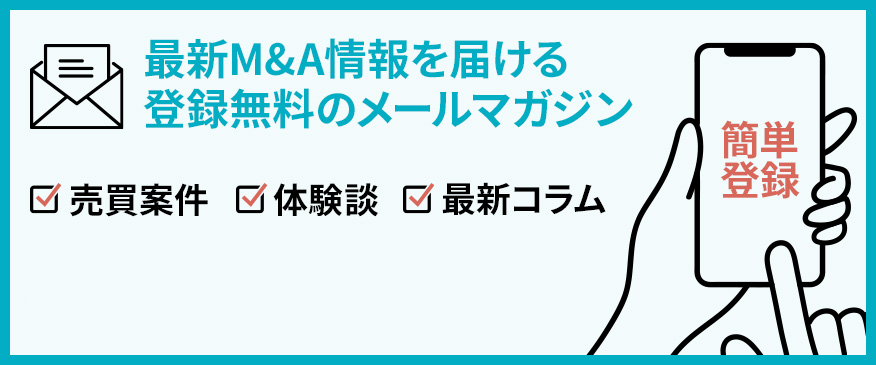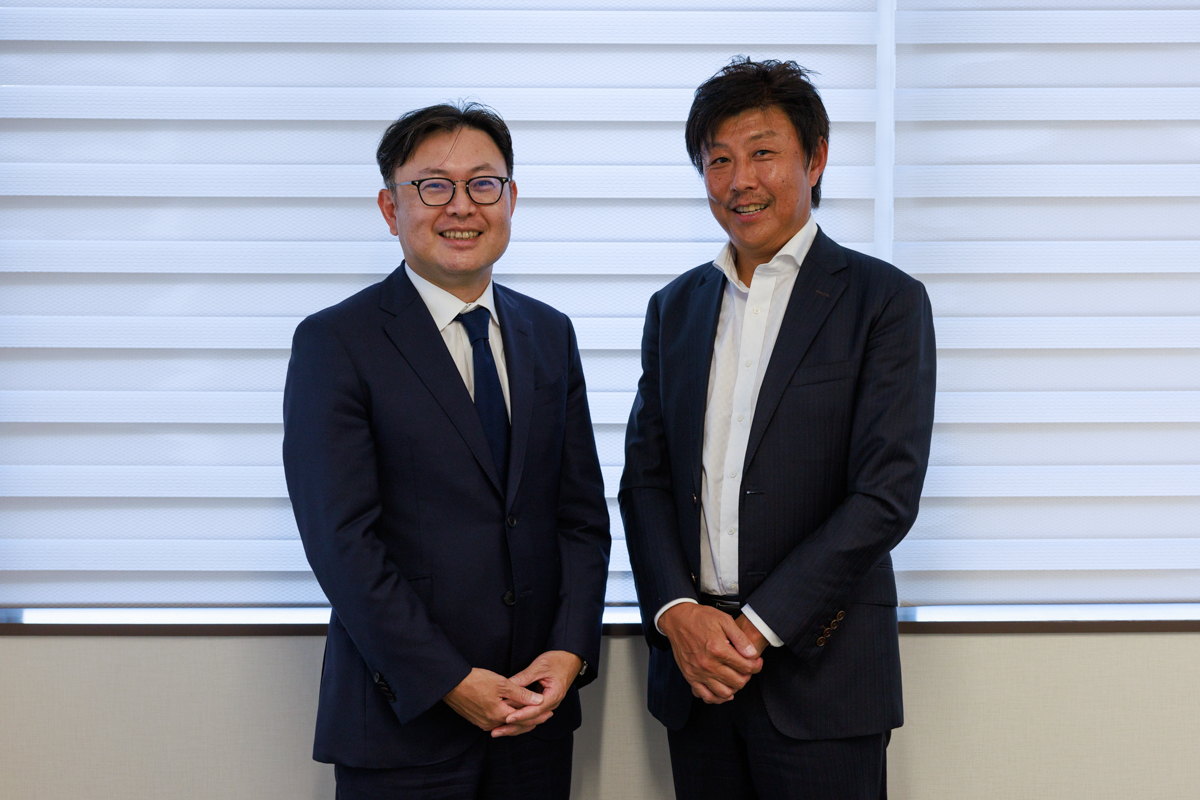ローカルM&Aマガジン
シナジー効果とは、M&Aが成立した後、会社をさらに成長させるために重要なファクターです。シナジー効果の活用なしにM&Aの成功はありません。
シナジー効果について、おさえておきたいポイントを解説します。
シナジー効果によって企業を一層成長させられる

シナジー効果とは、端的にいえば「相乗効果」のことです。
M&Aによって2つ以上の会社が一緒になり、それぞれの特徴や強みが掛け合わされて会社がより発展することを、「相乗効果が発揮される」と表現します。
シナジー効果を利用すれば、自社だけでは生み出せなかった新しい価値を、外部の力を吸収して生み出せるのです。
シナジー効果で得られる具体的なメリットとは?
ひと口にシナジー効果といっても、さまざまな種類があります。
どのようなシナジー効果があるのか、例をあげてみましょう。
①売り上げを大きく向上させる「売り上げシナジー」
「売り上げシナジー」とは、譲渡後の売上金額が、譲渡前の売り手・買い手両者の合計金額より大きくなることです。
たとえば、買い手企業はブランド力が強いものの生産力が弱く、売り手企業は生産力に強みがあるとしましょう。この2社が合併すれば、ブランド力の高い製品を大量に生産することができるようになります。
うまくいけば、M&Aによって業績を何倍、何十倍にも拡大できるでしょう。売り上げシナジーを得るのは、M&Aの代表的な目的です。
②大量仕入れにより生み出される「コストシナジー」
M&Aを行なえば、当然ながら会社の規模は大きくなります。そうして得たスケールメリットによって事業のコストを削減できるのが「コストシナジー」です。
たとえば、M&Aによる事業の大規模化で、大量仕入れが可能になり、原材料費を安く抑えられるようになる、といった効果がコストシナジーの代表例です。
コストシナジーはほかにも、「共通化コストシナジー」や「事業コストシナジー」、「税金シナジー」などに細分化されています。いずれにせよ、買い手と売り手の連携によりさまざまなコストの削減が期待できます。
③潤沢な財務基盤を確保できる「財務シナジー」
売り手の財務基盤が不安定な場合、資金が潤沢な買い手企業の傘下に入ることで資金余力の改善が期待できます。
キャッシュが少なかったり債務超過であったりというような財務上の弱点が、M&Aによる「財務シナジー」で克服できるのです。
④新商品開発のチャンスが得られる「研究開発シナジー」
M&Aによって買い手と売り手の得意な研究分野を融合させることで、新たな領域での研究開発を可能にする効果が、「研究開発シナジー」です。
買収によって、新たに獲得したノウハウと、もともと保有していた自社のノウハウとを組み合わせ、これまでに生み出すことのできなかった商品を開発できるようになるのです。M&Aを行なえば、相手企業の特許も使えるようになります。
⑤会社のブランド価値を上げる「信用力シナジー」
小規模企業の売り手が大企業である買い手の傘下に入ることで、高いブランド力を手に入れて高い信用力の獲得が期待できるシナジーです。
信用力シナジーによって、営業面で優位に立てるようになり、仕入れ先の開拓や採用面などにも幅広く効果を発揮します。
シナジー効果を活用するためのM&A戦略
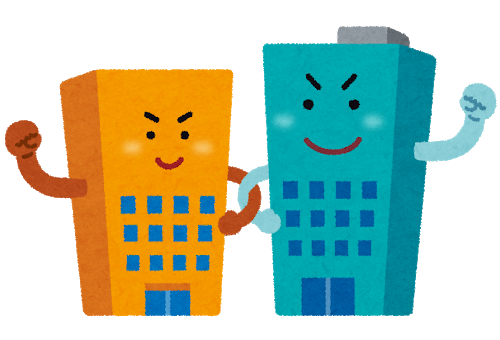
合併後に生まれるシナジー効果の判断は、基本的には買い手の主観に引っ張られる傾向があります。M&Aによるシナジー効果がどの程度発揮されるのかについては、合併前に正確に計算することが難しいためです。
ただ、売り手企業としては、M&Aによるシナジー効果の発生を価格に織り込んで、なるべく高値をつけて譲渡したいところです。
たとえば、コストエナジーのように数字で示すことができる指標については、比較的簡単に価格に織り込むことができます。具体的な根拠を可能な限り説明し、買い手企業にシナジー効果を納得してもらい、M&A交渉を有利に進めましょう。
まとめ
M&Aによるシナジー効果を売り手の側で整理する作業は、自社の価値を再認識し、高めることにつながります。
双方がシナジー効果を明確に認識したうえでM&Aが行なわれれば、合併後のさらなる両者の発展に一歩近づきます。
買い手と売り手、M&Aアドバイザリー会社などの関係者同士で、合併によってどんなシナジー効果が生じるのかを十分に議論して進めましょう。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役