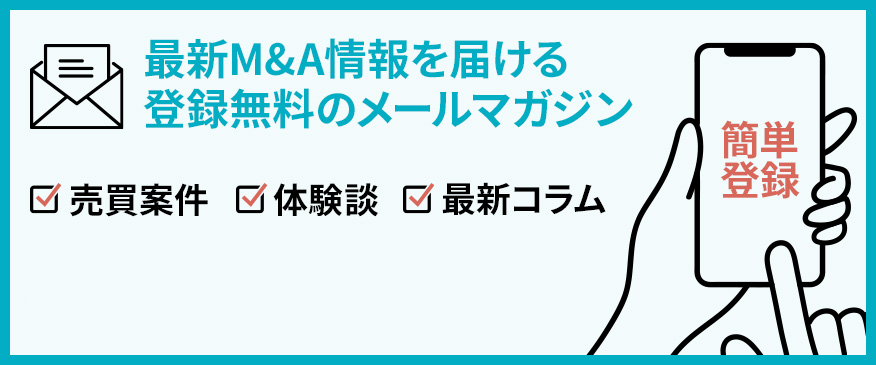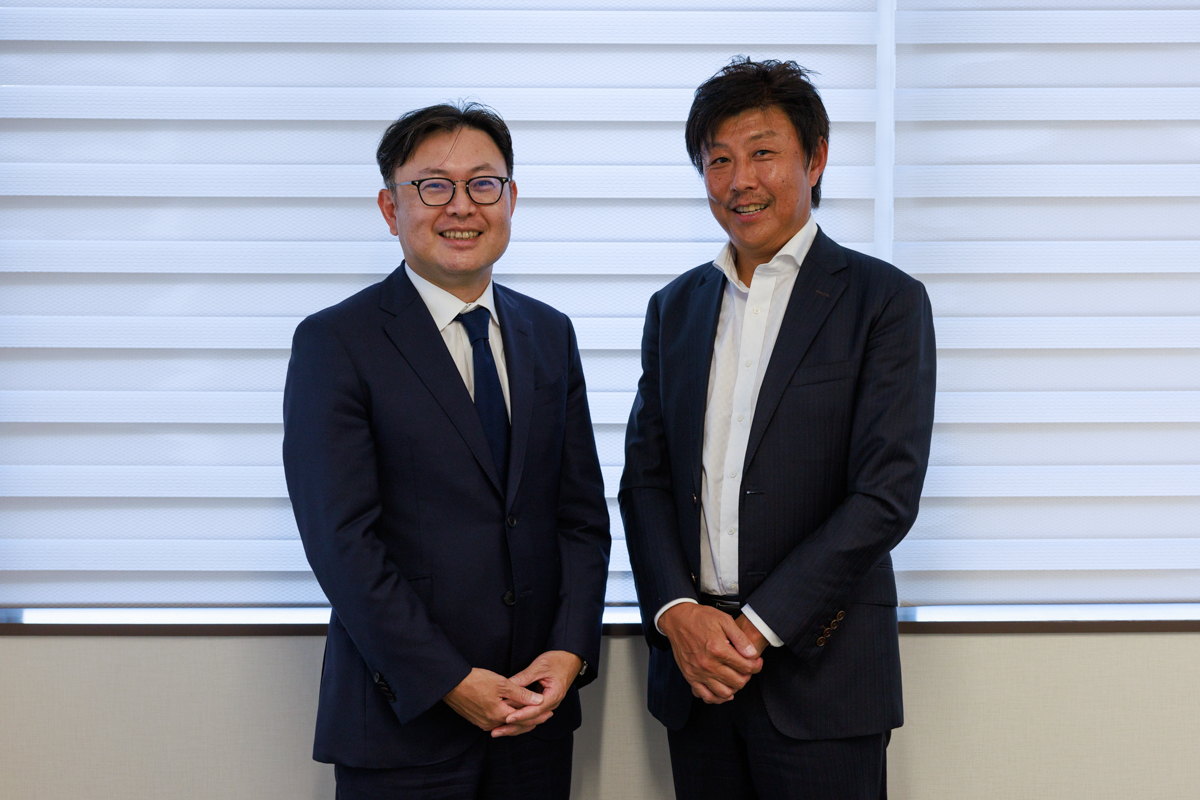ローカルM&Aマガジン
同社の株式の51%を保有するベインキャピタルは同社の株式を売却し、雪国まいたけは、49%の株式を保有していたコメ卸会社大手の神明の連結子会社になることになります。
珍しいM&Aのケースとして話題になった雪国まいたけについて、M&Aコンサルタントとしての見地から分析しましょう。
不可能と言われたまいたけの人工栽培に成功

雪国まいたけは、創業者の大平喜信氏が1975年に創業した「大平もやし店」をルーツとします。
1982年には、希少さから「幻のキノコ」と言われたマイタケの人工栽培に着手。1983年には、日産350kgの人工栽培を成功させます。同時に、株式会社雪国まいたけが設立されました。
1994年には新潟証券取引所地域産業育成部に上場、2000年には新潟証券取引所と東京証券取引所の合併により、東証2部に株式を上場することになりました。
創業以来、不可能に挑戦し続ける大平氏のベンチャー精神を原動力に、まいたけだけでなくぶなしめじやエリンギ、またそれらの加工食品や健康食品などを手がける大企業への順調に成長してきた雪国まいたけ。2020年時点でまいたけの市場シェアが50%を超える同社ですが、2015年に大波乱を経験しています。
驚きのTOB劇

2015年2月、ベインキャピタルが雪国まいたけへのTOBを実行しました。ただ、その時点で雪国まいたけは創業者一族が株式の3分の2以上を保有しており、TOBが成功してもベインキャピタルの持株比率は3割程度にしかなりません。
にもかかわらず、TOBの実行によってベインキャピタルは筆頭株主になることができました。その理由は、メインバンクの第四銀行が創業者の持つ株式に対して担保権を行使したことです。
第四銀行は、創業者である大平喜信氏の資産管理会社と大平氏個人が持つ株式を担保に、雪国まいたけへ融資をしていました。融資の返済が滞っていた同社に対し、第四銀行が担保権を行使することによって筆頭株主に。そして最終的に創業者の株はベインキャピタルの手に渡り、TOBが成立することになりました。
しかし、雪国まいたけは融資の返済が滞っていたとはいえ、金利に相当する程度には借金を返済していたといいます。なぜそれでも担保権の行使が認められたのかというと、背景には創業者一族と現経営陣との骨肉の争いがあります。
雪国まいたけは創業者である大平喜信氏の典型的ワンマン経営で、振り回される社員の側には相当のうっぷんが溜まっていました。そして、元取締役が過去の不正会計を告発したことで、大平氏は引責辞任することになります。
ところが、大平氏が辞任した後も、創業家が大株主としての権力を使って雪国まいたけに介入していきます。
後任の社長を一方的に解任する、株主総会で圧力をかける、創業家の息がかかった取締役を送り込もうと画策する……2015年当時の同社は、深刻なガバナンスとコンプライアンスの問題の渦中にいたのです。
もはや、市場でも地元でも「雪国まいたけは危ない」というのが定説になっていました。このトラブル状態を第四銀行も深刻に受け止め、創業者一族を排除する計画に一枚噛むこととなりました。そして見事な奇策により、最終的にベインキャピタルの買収が成功することになったのです。
まとめ
中小企業の経営者がこのケースを聞くと、「融資の担保にした株式を銀行に取られた」という事実に大きな衝撃を受けるでしょう。
オーナー経営者の資産会社や個人の持つ株式を担保にして融資を受けている会社はたくさんあります。また、返済といっても利息相当の額を細々と返済しながら銀行との付き合いを続けている、という会社は珍しくありません。
銀行が担保権を実行するにはそれ相応の理由があったものと考えらます。融資を受ける際に銀行取引約定書にハンコをつきますが、そこには担保権を実行する条件が記載されております。その契約の基づき、第四銀行はオーナーの株式を返済の代わりに取得したのでしょう。
銀行との間にどんなやりとりがあったかはわかりませんが、銀行が実力行使して、オーナー社長の支配権が奪われてしまった珍しいケースです。
ただ実際は、雪国まいたけのように極端な担保権の行使がされることはあまり考えられないでしょう。
同社は創業家と社内の対立によりガバナンスとコンプライアンスがめちゃくちゃな状態で、それが社会にも広く知れ渡っていました。銀行としても、経営体制が安定しない状況が長く続くことを見逃せず、ファンドと手を組んで間接的に買収に加担するに至ったのでした。特例的な対応と言えるでしょう。
TOBから5年、再上場を果たし、時価総額800億円超となった雪国まいたけ。今後の動向から目を離せません。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役