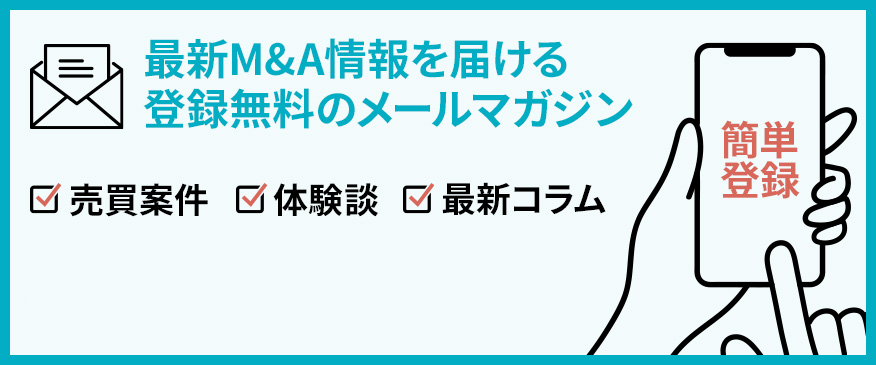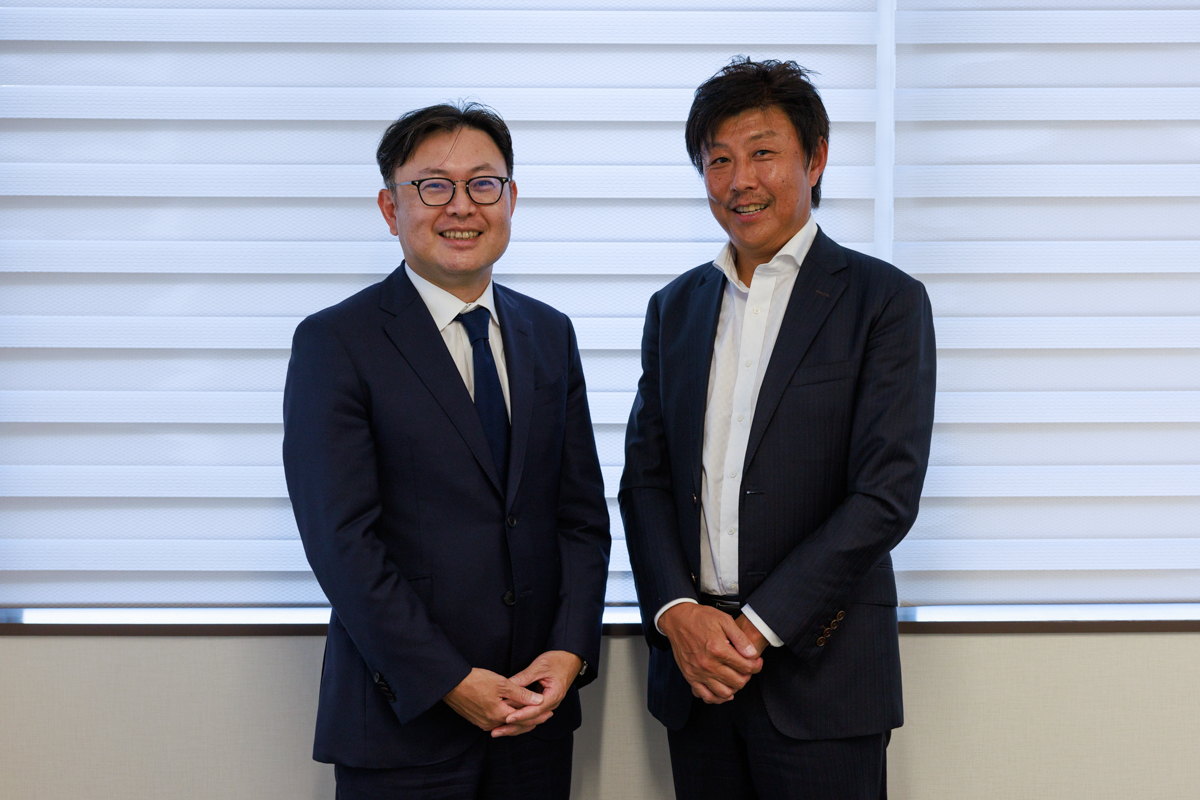ローカルM&Aマガジン
経営者の中には、聞いたことがない、あるいは聞いたことはあるけれども詳しい内容は知らない、という方が多いかもしれません。
事業承継の5ヶ年計画とは何なのか、中小企業にとってどのようなメリットがあるものなのか、解説します。
事業承継の5ヶ年計画とは?

中小企業の多くが後継者不足に陥り、事業承継が社会問題になって久しい昨今。
中小企業庁が事業承継問題に取り組む、今後5年間の集中的な施策をまとめたのが、事業承継の5ヶ年計画です。
事業承継の5ヶ年計画においては、大まかに以下の5つのような支援の方向性が掲げられています。
① 経営者の「気付き」の提供
② 後継者が継ぎたくなるような環境を整備
③ 後継者マッチング支援の強化
④ 事業からの退出や事業統合等をしやすい環境の整備
⑤ 経営人材の活用
一つずつ見てみましょう。
①経営者の「気付き」の提供
事業承継において多く見られるのが、経営者も何となく継承を意識はしていながら具体的な行動に出ず、時間が経ってしまううちに経営者の健康悪化などで一気に問題が顕在化するケースです。
事業承継の5ヶ年計画では、事業承継について経営者に早期の対策を促すべく、「事業承継のプレ支援のプラットフォームの構築」を掲げています。
具体的には、5年間で25万〜30万社を対象にプッシュ型の事業承継診断を実施すること、事業承継支援を行う人材の育成・活用を促進することをうたっています。
②後継者が継ぎたくなるような環境を整備
事業承継が遅々として進まない要因には、昨今の人々の生き方が多様化したことなどを背景として、家業を「継ぎたくない」と考える後継者が増えたことが挙げられます。
事業承継の5ヶ年計画では「早期承継のインセンティブの強化」を掲げています。
施策の方向性としては、「後継者による新機軸・業界転換等の経営革新を支援」「小規模事業者が強みを発見するための事業計画作成支援」「資金繰り・採算管理等の早期段階からの経営改善の取組を支援」「再生施策との連携強化」「事業承継税制の更なる活用を図る」などです。
後継者がまず心配する会社とお金の問題の支援、また先代とは違った経営のあり方をサポートすることを目指しています。
③後継者マッチング支援の強化

昨今は売上10億円以下のスモールM&Aマーケットが活況を呈していますが、中小企業庁としても「小規模M&Aマーケットの形成」を施策の方向性の一つとして定めています。
既に全国47箇所に設置されている事業引き継ぎ支援センターの機能を強化し、支援センターが保有するM&A対象企業データベースの拡充、開示範囲の拡大、また民間のデータベースとの相互乗り入れが計画されています。
④事業からの退出や事業統合等をしやすい環境の整備
中小企業は特定の企業との下請け関係に依存していたり、地域経済のしがらみに縛られていたりするケースが少なくありません。そのような経営環境も、事業承継や廃業の決断を妨げる要因です。
事業承継の5ヶ年計画では、「サプライチェーン・地域における事業統合等の支援」を掲げています。
下請振興法にメスを入れて、自主行動計画に事業承継に関する取組を明記し、自主行動計画のフォローアップを実行。また、中小企業の再編や統合を促す制度的な枠組みを検討し、承継の当事者だけでなく業界全体で事業承継をバックアップする施策を進める、としています。
⑤経営人材の活用

最後である5つ目の方向性は、「経営スキルの高い人材を事業承継支援へ活用」することです。
地方の中小企業の場合、経営スキルを持った人材を独力で発掘してくることは困難です。そこで、中小企業庁の主導で人材紹介会社と事業引継ぎ支援センターとの連携を促進し、経営スキルの高い人材を中小企業の後継者として呼び込む施策を掲げています。
また、経営人材を後継者に据えることでインセンティブが発生するような施策も検討しているようです。
まとめ
以上が、事業承継の5ヶ年計画の大枠です。
なお、さらに詳細な解説については、中小企業庁による以下の資料が参考になります。
中小企業の事業承継に関する集中実施期間について(事業承継5ヶ年計画)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170707shoukei1.pdf
方向性通りの施策が積極的に実行されれば、事業承継に悩む中小企業の多くが救われる内容になっています。
政府や自治体の施策では、施策自体は優れていても知名度不足で利用者がいないものが少なくありません。経営者自身で情報を集め、使える制度はすべて使っていくことが重要になります。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役