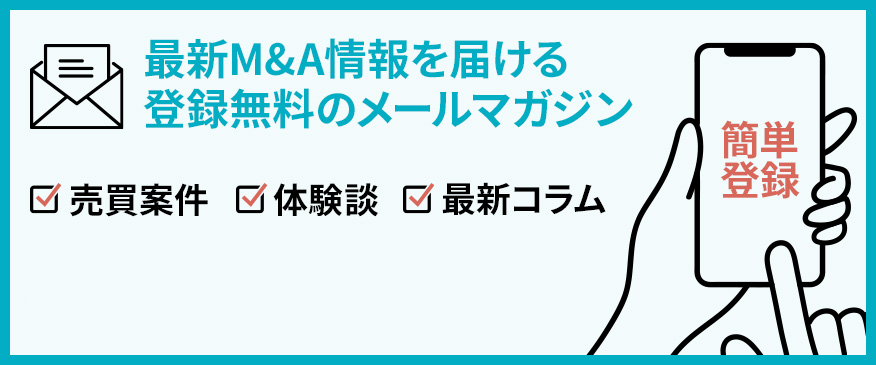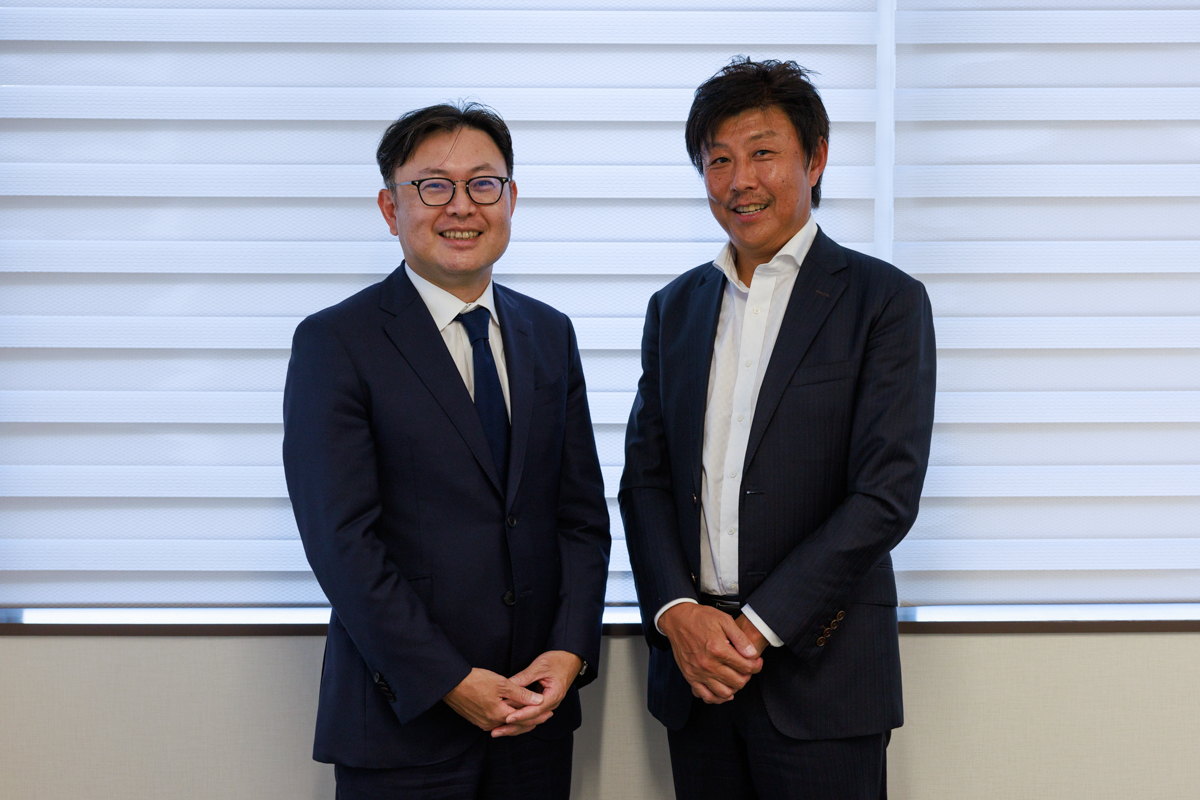ローカルM&Aマガジン
事業を承継して経営者が引退したり、古株の取締役が引退したりする際に退職金を支払うケースは多いと思いますが、退職金の金額が大きければ、損金算入が認められないことがあります。
退職金が過大退職金と見なされるリスクと、リスクを避けるコツについて解説します。
「引退後は退職金で悠々自適!」のはずが……

事業承継でようやく経営者の重荷を降ろし、引退後は退職金で豊かに暮らす……そのようなライフプランを描く経営者は多いでしょう。
また、長年右腕となってくれた取締役の退職に際し、その労をねぎらうために退職金を支給するというのも、非常によくあるケースです。
しかし、この役員退職金が、金額が過大だとして損金参入が認められない場合があるのです。
「過大である」と判断されると、損金参入が認められない!?
「過大役員退職金」の問題で頻発するのは、税務署から「過大である」と判断された分の金額について、損金算入が認められないケースです。
多くの場合、「役員退職金」は、法人税の軽減や事業承継に際しての株式価値の軽減、支給対象個人に対する贈与税や所得税の軽減などを見込んでいます。しかし、狙いが外れて「過大退職金」と見做されれば、事業承継計画は大きく狂い、場合によってはキャッシュフローが崩れて経営自体が深刻なダメージを受ける危険もあるのです。
なかには、「役員退職金」として認められない場合も
さらに怖いのは、過大分のみならず、支払った全額が「役員退職金」として認められないケースです。
実は、「退職金」は以下の3つの要件を満たさなければなりません。
② 従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること
③ 一時金として支払われること
ただし、上記の要件を全て満たしていなくても、「退職金」としての性質を実質的に満たしていれば、「退職金」として認められるケースもあります。
「役員退職金」と認められなかった場合
先の話に戻れば、支払った全額が「退職金」と認められなかった場合、税務上のデメリットが非常に大きくなります。
法人の側からすると、役員給与は事前に決定していた分だけが損金算入できるため、否認されれば退職金の全額を損金にできなくなってしまうのです。
また、受け取る個人の側も、退職金が退職給与と認められなければ、通常の給与と同じく所得税の累進課税の対象になってしまうので、所得税が非常に高くなってしまう危険があります。当然、翌年度の住民税にも影響が出ます。
「役員退職金」として認めてもらう3つのポイント
それでは、「役員退職金」としてしっかり認められるためには、具体的にどうすればいいのでしょうか?
ポイント1・一般的な計算式に沿って支給する

一般的な退職金の計算式は、「最終の役員報酬月額×役員勤続年数×役員としての功績倍率」となります。
この計算式から大きく外れた退職金額を設定すると、退職金として認められないリスクが一気に増大します。
ポイント2・税理士に相談しながら正当な「功績倍率」を設定する

最終の役員報酬月額と勤続年数は、退職直前になってから操作することが困難です。したがって、退職金額の決定については、「役員としての功績倍率」をどれくらいに設定するのかが、最大の論点になります。
功績倍率とは、同業類似法人の功績倍率の平均値又は最高値とされているのですが、実際には、昭和55年の裁判において、国が示した「社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」が採用される場合が多くなっています。
しかし、退職金を認めるかどうかは、最終的に税務署が決定することになるので、事前にラインを設定するのは困難。同業同規模の企業の事例がわかるならそれを参考にし、税理士に相談しながら決めることをおすすめします。
ポイント3・小細工は通じない?

まれに、退職金の計算額を大きく上げるために、退職予定の最終期の月額を大きく引き上げようとする経営者がいます。
しかし、退職金と同じく役員給与についても、不当に高額であれば、やはり損金に参入されません。
過大な支給が損金不算入となってしまうリスクは、結局避けられないのです。
まとめ
以上、「役員退職金」が損金として認められないケースについて解説してきました。
これらのリスク対策は重要ですが、リスクを恐れるあまり「役員退職金」を不当に低く設定してしまうと、元も子もありません。法人税の軽減と、役員の引退後の資産増という本来の目的が果たせなくなってしまいます。
信頼できる税理士に相談しつつ、損金算入しながらなるべく大きな額の退職金を設定できるよう調整することが大切です。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役