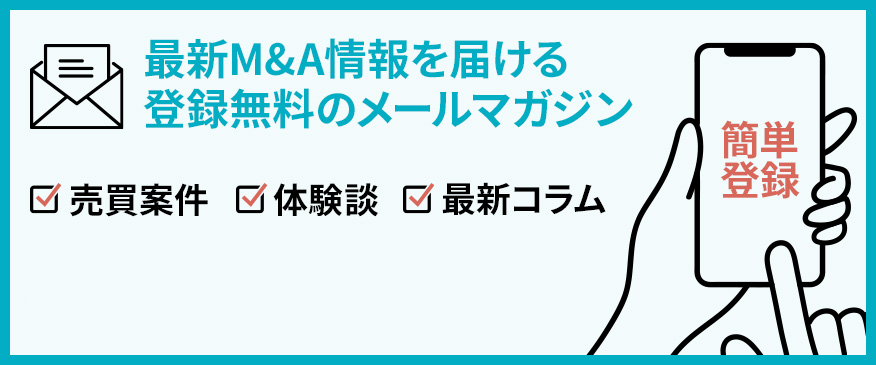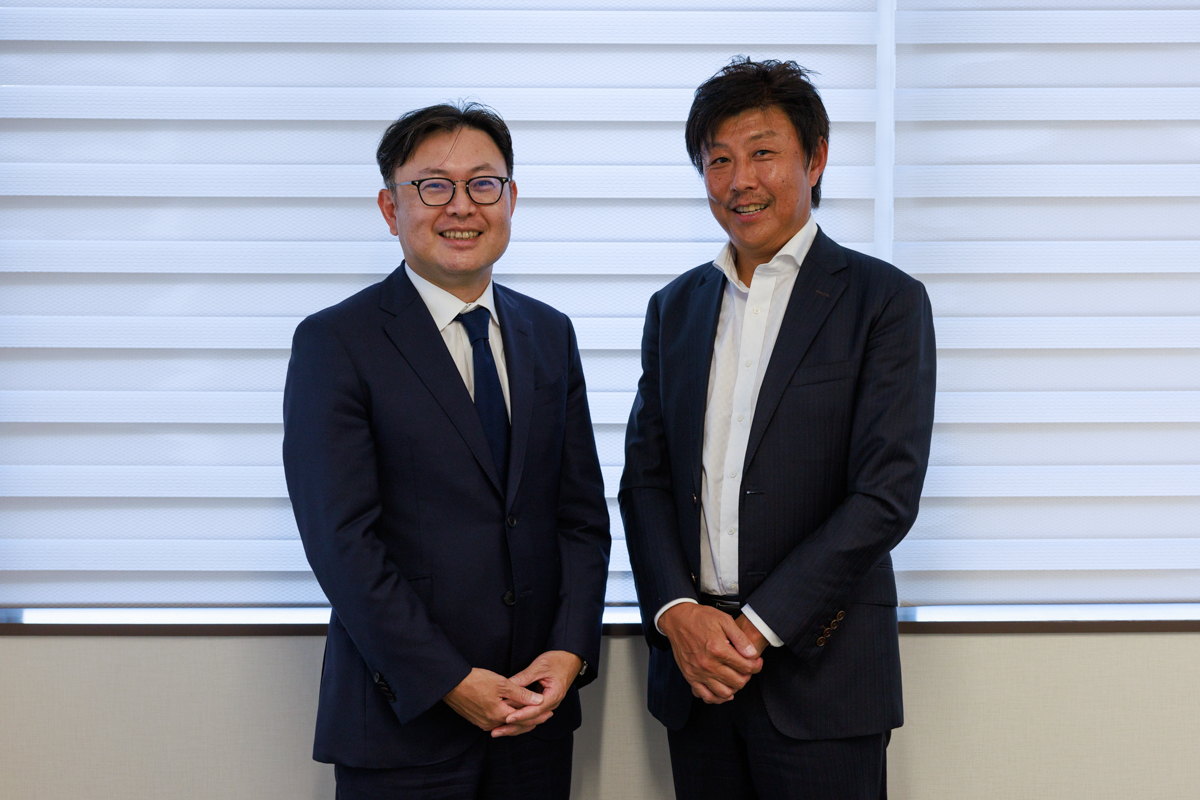ローカルM&Aマガジン
当社のもとに、このような相談でいらっしゃる2代目社長、3代目社長が増えてきました。ある人はやる気満々で、ある人はおっかなびっくりで先代から会社を継ぐわけですが、その後の経営の中でM&Aでの売却を検討するようになる人が多いようです。
なぜ、承継社長の多くが後悔し、会社を手放したがる結果になってしまうのでしょうか。
承継を後悔する理由

中小企業庁のデータでは、事業承継にまつわる3つの後悔として以下のような内容が紹介されています。
①財務の会計の引き継ぎの後悔
承継にあたっては当然、先代社長から会社の事業について引き継ぎを受けるわけですが、この際に決算書類の詳細までは丁寧に説明されないこともあります。また、継ぐ側としても当初は財務や会計のことなど何もわからないまま社長になる、というケースも多いようです。
その結果、継いでから初めて知識をつけ、自分の会社の財務内容の厳しさを実感。「これではこの先やっていけない」となってしまうのです。
②資金調達ノウハウの引き継ぎの後悔
銀行をはじめとする金融機関から、資金調達する方法を身につけておかなかったことで苦しむケースも多いようです。
「社長の仕事は金集めだ」と断言する人もいるほど、経営者にとって資金調達は重要な仕事。先代社長のときは金融機関との関係性ができていてスムーズに資金調達ができていたのが、何もわからない承継社長が窓口になると融資が急に絞られるケースは少なくないようです。
営む業種によっては、事業の継続に借り入れがほぼ必須なこともあります。資金調達ができなくなれば一気に窮地に陥ってしまうのです。
③会社と個人の借入金の引き継ぎの後悔
「蓋を開けてみたら借金の多さにびっくり」というのは、後継社長に非常に多いケースです。特に、経営者で連帯保証している多額の債務を引き継ぐ場合、後継社長個人に対しても大きな重圧がのしかかってしまいます。
こんなに借金があるなら継いでいなかったのに……となってしまうのです。もし事前に説明を受けていたとしても、会社の借り入れを自分で保証する感覚というのは、体験しないとなかなか理解できるものではありません。実際に後継社長が当事者になってみて初めてそのプレッシャーを実感し、後悔するようになる人が多いのです。
なお、現在では「経営者保証ガイドライン」というものがあり、先代社長の個人保証の引き継ぎについて以下のように定められています。
・原則として前経営者、承継者の両方からの二重徴収は行わない。(例外あり)
・経営者保証の引き継ぎにより事業引き継ぎが頓挫する場合など、当然に保証を引き継ぐのではなく、総合的な判断として経営者保証を求めない対応ができないか真摯かつ柔軟に検討することが債権者に求められる。
・保証を引き継ぐ場合も、資金使途に応じて保証の必要性や適切な保証金額の設定を設定するなど、代替策の検討が債権者に求められる。
通常の引き継ぎにおける経営者保証が簡単に解除できるようになったかというとそういうわけではありませんが、債権者の側により丁寧で適切な説明を求めるものになっています。
経営者保証ガイドラインについては、以下のウェブサイトで詳しく紹介されています。
・事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の策定について
https://www.jcci.or.jp/chusho/tokusoku.pdf
人間関係で悩む後継社長も

ここまで挙げた要因以外に、従業員や取引先との関係性に苦しんで後悔する承継社長もいます。
特に中小企業の場合、今いる従業員は「先代についてきている従業員」であることが多いものです。後継社長が会社を継いでも、彼ら・彼女たちにとって後継社長のイメージは「社長のぼっちゃん、娘さん」のまま。結果、後継者としてリーダーシップを取ろうとしても思うようについてこない、という状況になってしまいます。舐められてしまうのです。これは取引先についても同様で、先代のときにはうまくいっていた交渉が急にギクシャクするケースも見られます。
先代社長が事業承継後も会長などとして会社に残っていると、余計にやりづらくなります。代表権や株式を後継者に受け渡したとしても、実質的な権力者としてあれこれと口を出してくるパターンが多いのです。後継社長としては、自分がオーナーであるはずなのに慣例的に先代へいちいちお伺いを立てなければいけず、まるで院政の傀儡政権のようになってしまいます。こんな状況では、後継社長としての活躍ができようはずもありません。
まとめ
事業承継は失敗することも多く、決して簡単ではありません。先代が創業社長で絶対的なカリスマ性を持っていたりする場合は、なおさらでしょう。
長年にわたっての経営の結果としての財務状況や社内の関係性など、後継社長にはどうしようもない問題を会社が抱えていることもあります。意地になって社長を続けて苦しむのであれば、M&Aで売却してしまうのも選択肢です。一回継いだ手前、気が引けるかもしれませんが、先代にいくらか持ち株が残っている場合、M&Aが成功すれば後継社長だけでなく先代にも売却益が入ります。結果的に双方にとってメリットです。
経営状況がどんどん悪化してM&Aすらできなくなる前に、早めに検討したほうがいいでしょう。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役