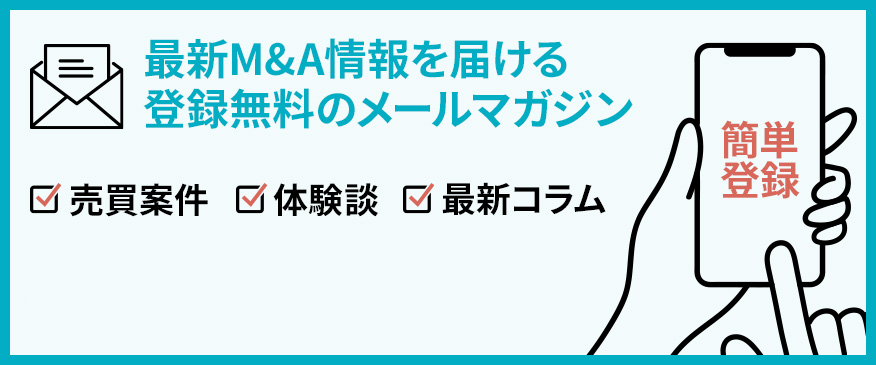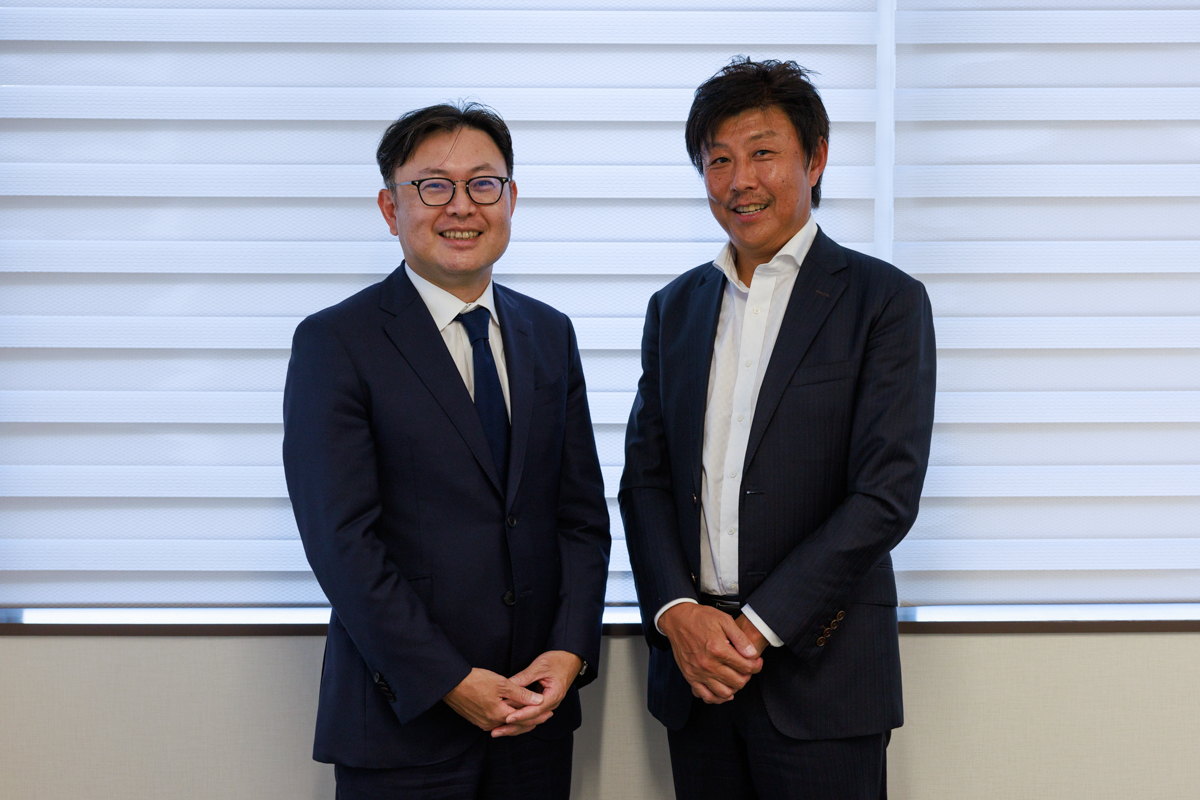ローカルM&Aマガジン
そして、M&Aを思い立った際の相談窓口になるのが、各都道府県に設置された「事業引き継ぎセンター」です。
事業引き継ぎセンターの仕組みやかかる費用、相談するメリットとデメリットについて解説します。
事業引き継ぎ支援センターとは
事業引き継ぎ支援センターとは、中小企業や小規模事業者の事業承継を支援する公的機関です。全国で47箇所に存在し、当社が拠点を置く新潟県にも事業引き継ぎ支援センターが置かれています。
事業引き継ぎ支援の流れ

あなたが事業引き継ぎ支援センターに相談した場合、まずは担当者との面談がセッティングされます。
面談の結果、事業引き継ぎの支援が必要と判断されれば、中小企業基盤支援機構が持つ事業引き継ぎデータベースにあなたの会社が登録され、その後マッチングした場合は事業引き継ぎ支援センターのサポートによってM&Aを進めていく流れになります。
中小企業基盤支援機構とは中小企業の経営をサポートするために設立された独立行政法人で、新規事業創出のための各種連携サポートや助成金の受付などを行っています。
事業承継においては、データベース管理を通じてM&Aのマッチングのプラットフォームを形作るのが役割です。他、後継者人材バンクというデータベースも管理しています。民間のM&Aアドバイザリー業者の中から、認定支援機関として連携し、案件を一緒に進めることもあります。
絆コーポレーションも新潟県事業引継ぎ支援センターの認定支援機関になっております。
事業引き継ぎ支援センターに相談するメリット
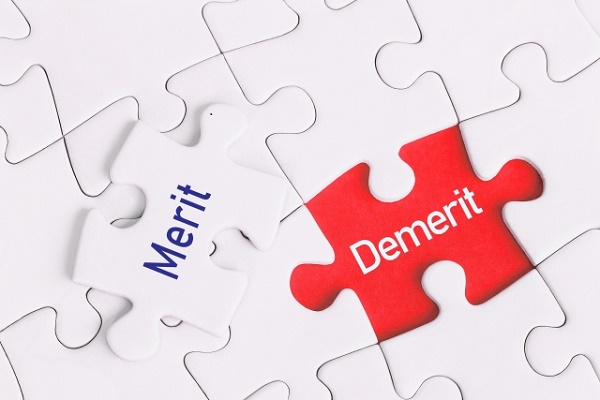
事業引き継ぎ支援センターは、中小企業庁の直轄による公的機関です。
民間のM&A業者の質は玉石混交で、着手金だけ取られてその後全然動いてくれないといったケースもあるので、公的機関である事業引き継ぎ支援センターに相談すればまずは安心できるメリットがあります。
また、もう一つの大きなメリットは費用です。民間の業者は相談をするだけで費用がかかることもありますが、事業引き継ぎ支援センターは何度でも無料相談ができます。キャッシュに余裕がなかったり、具体的なM&Aの検討をする前にまず概要だけ知りたかったりする場合に気軽に相談できるでしょう。
事業引き継ぎ支援センターへの相談件数は年々増加しており、中小企業基盤支援機構の発表によれば、2012年には約900社だけだったのが、2019年には11,514社にまで相談件数が増えています。
参考:令和元年度 事業引継ぎ支援事業に係る相談及び事業引継ぎ実績について
(https://www.smrj.go.jp/org/info/press/2020/favgos000000rl43-att/20200730_press_01.pdf)
デメリットとリスクは?
公的機関のネットワークを用いながら費用を抑えたM&Aを目指せる、事業引き継ぎ支援センターの活用ですが、デメリットも存在します。
民間のM&A業者のほうが熱心?
事業引き継ぎ支援センターは前述の通り何度相談しても無料です。なぜなら、国から予算が割当てられており、担当者は地元地銀からの出向や地元の士業の方が業務を委託されて運営しているからです。会計士などの専門家のサポートを受ける場合に報酬を支払うのみですが、その分、あなたの会社のM&Aを成立させてもさせなくても、自分の給与には反映されない、いわば準公務員なので、全力を注いでくれることはあまり期待できない可能性もあります。
そういった意味では、民間の業者に相談した場合のほうが熱意を持って案件に取り組んでくれる場合もあることは知っておいたほうがいいでしょう。もちろん、営利目的のM&A業者が取り組むことがすべてにおいてベターであるとは言い切れない面もあることには、注意してください。
事業引き継ぎ支援センターへの相談にしても、担当者次第な部分もありますが、民間の場合は業者選びがますます重要になります。
ネットワーク力は民間のほうが優れていることも
また、中小企業基盤支援機構のデータベースが政府のネットワークだからといって、それだけでM&Aのマッチングプラットフォームとして十分に機能するとは限りません。
特にM&A案件の件数が少ない地方都市の場合、地域密着でM&Aコンサルティングに取り組む業者のほうが豊富なネットワークから事業継承者を見つけ出し、募集できることもあり得ます。
会計士や弁護士といった士業のプロとの連携についても同様です。当社の経験上、M&Aの案件経験が豊富で実力のある先生ほど仕事に困っておらず、信頼するM&A業者からの紹介でないと依頼が難しいケースもあります。
まとめ
事業引き継ぎ支援センターにM&Aを相談することには、以上のとおりメリットとデメリットが双方存在します。
ただ、やはり無料相談ができるのは大きいでしょう。民間の業者は何社も自分で探して会いにいくのが手間ですし、相談するだけでお金がかかる場合もありますから、まずは事業引き継ぎセンターに出向いて感覚をつかむ、というのはいい選択だと思います。
その上で、誰をM&Aのパートナーにするのかを考えればいいのです。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役