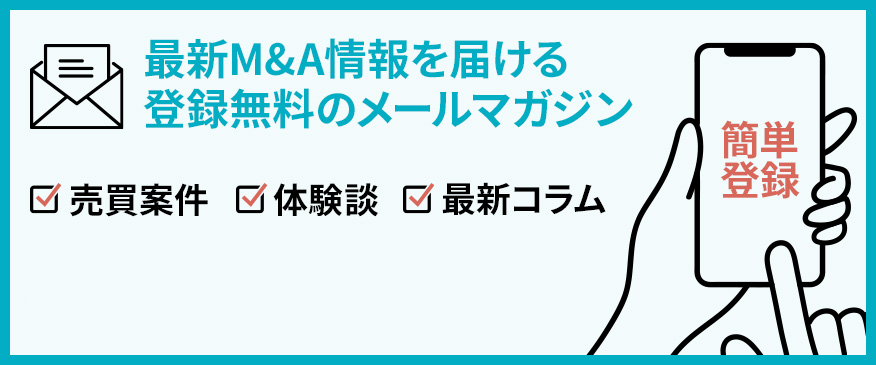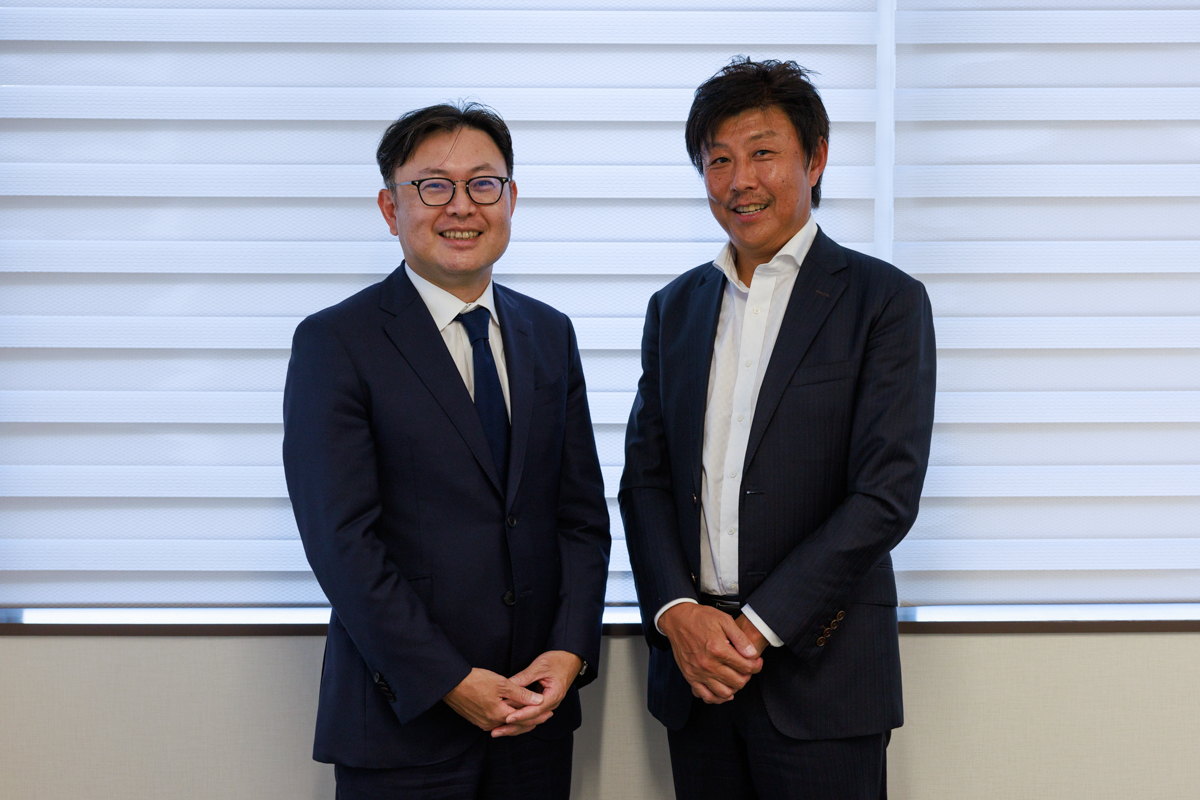ローカルM&Aマガジン
そんななかで、「ファンド」が買い手になるM&Aの例も見られるようになっています。
中小企業にはあまり馴染みのない、ファンドへの売却という選択肢。
今回の記事では、ファンドが買い手になるM&Aの特徴を見てみましょう。
中小企業を買収するファンドとは?

ファンドと一口にいっても、さまざまな種類が存在します。
まずは、中小企業のM&Aにはどのようなファンドが関わるのかを解説しましょう。
上場株式を買うファンドと非上場株式を買うファンド
まずファンドとして代表的に知られているのは、「ヘッジファンド」です。
ヘッジファンドとは、基本的には株式上場している企業を対象として投資を行なうファンドです。
支配権を取れる割合以上の株式を取得して経営に関与するのか、経営権は取らずに出資するのかはそのファンドによって異なります。
いずれにせよ、株式市場のなかで収益を狙うため、ヘッジファンドは非上場企業のM&Aには取り組みません。
同様に上場企業を対象にしたファンドとして「アクティビスト」と呼ばれるファンドもあります。
アクティビストはさまざまな上場企業に少しずつ出資し、「物言う株主」として強い株主要求を出すことで出資先の経営を改善し、株価を上げて売却することを狙います。
これも中小企業には無関係といえます。
中小M&Aに関わるのは、「PEファンド」!
非上場企業のM&Aで買い手となりうるのは、「PEファンド」と呼ばれるファンドです。
PEとは「Private Equityプライベート・エクイティ」の略で、非上場企業の株式を購入するファンドを総称して「PEファンド」と呼びます。
よく聞くVC(ベンチャー・キャピタル)も、大きなくくりではPEファンドの一種です。
そしてPEファンドのなかでも、「事業承継ファンド」などと自称して優良な中小企業の株式をほぼ全株購入し、経営関与(ハンズオン)による時価総額向上を狙うファンドが存在します。
中小企業にとってM&Aの売り先になりうるのはこの種のファンドで、最近では東京都が出資したファンドなど、中小企業を対象にするファンドも出てきています。
なお、VCについても絶対にスタートアップにしか投資しないとは限らず、再成長を狙う老舗企業に出資するケースもあります。
そういう意味では、VCも中小企業のM&Aで買い手になる可能性はあるのです。
ファンドによるM&Aのメリット・デメリット
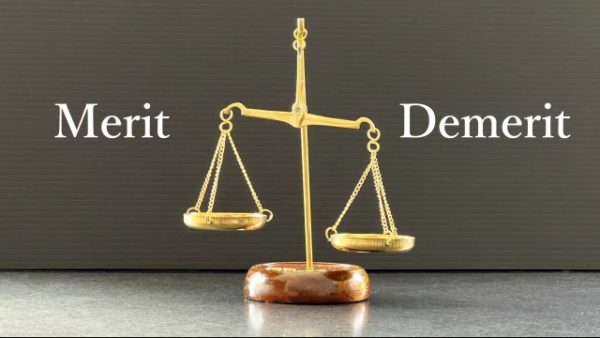
続いて、ファンドを買い手としてM&Aを行なうメリットとデメリットを見てみましょう。
メリットは、圧倒的な資金力の活用
ファンドによるM&Aが持つ最大のメリットは、豊富な資金を生かせる点です。
ファンドによって投資基準は異なりますが、通常、数億円から数十億円単位の資金が買収先の企業に注入されます。
一方、ファンドは投資家ですから、その投資額に対して何%のリターンを得られるのか、事業会社に比べてかなりシビアに見られます。買値についても厳しく交渉されるのが通常です。
さらに、経営幹部をはじめとする人材面についても、新規採用したり人員を送り込んだりといった判断はファンド主導で進められます。
ファンドが最大の投資対効果を目指すための施策が、買収先の従業員にとっても最良なのかは、非常に難しいところです。
デメリットは、株式を持ち続けてくれないこと!
デメリットとしては、投資期間が終わったら株式を再度売却されてしまう点です。
ファンドには必ず出資元があり、ファンドは一定期間(5年から7年がひとつの目安)が過ぎたら収益を確定させて出資元にリターンをもたらさなければいけません。
したがって、ファンドが入ると一定期間後のEXIT(出口戦略)はセットです。そのEXITは2つです。ひとつはIPO(株式の上場)でリターンを求めるのか、もう一つはその会社の事業の価値を高め、M&Aで投資した株価より高い株価にして、売却益を狙うことです。
フォンドを運営しているのは百戦錬磨の金融スペシャリストなので、企業価値を高めるためのノウハウ知識や経験には秀でています。しかし、同じ経営者の元での事業永続という観点からはかけ離れてしまいます。そこは賛否両論であり、何を求めるかによって、フォアンドを売却先の選択肢のひとつに入れることも悪くはないでしょう。
まとめ
M&Aの売却先としてのファンドは、選択肢の一つです。
ただ、ファンドは地方都市の中小企業とあまりに違った論理で動いており、中小企業にはなじまないケースが多いでしょう。
売却後も自社が永続的に発展することを望むのであれば、本業として事業を行なう会社がいいのかもしれません。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役