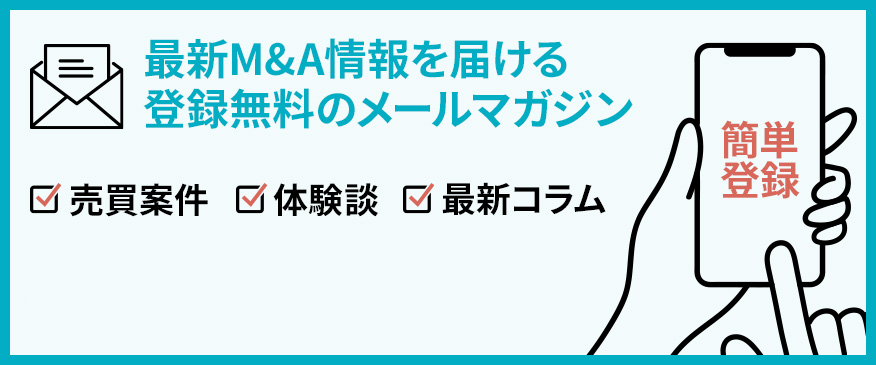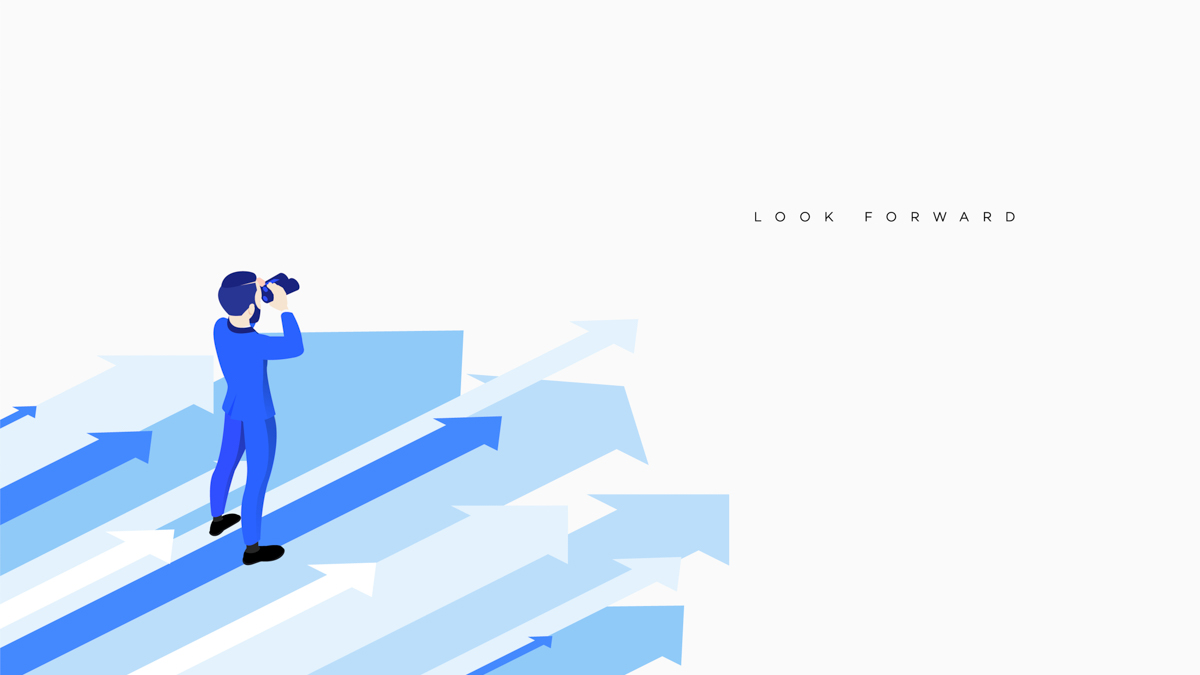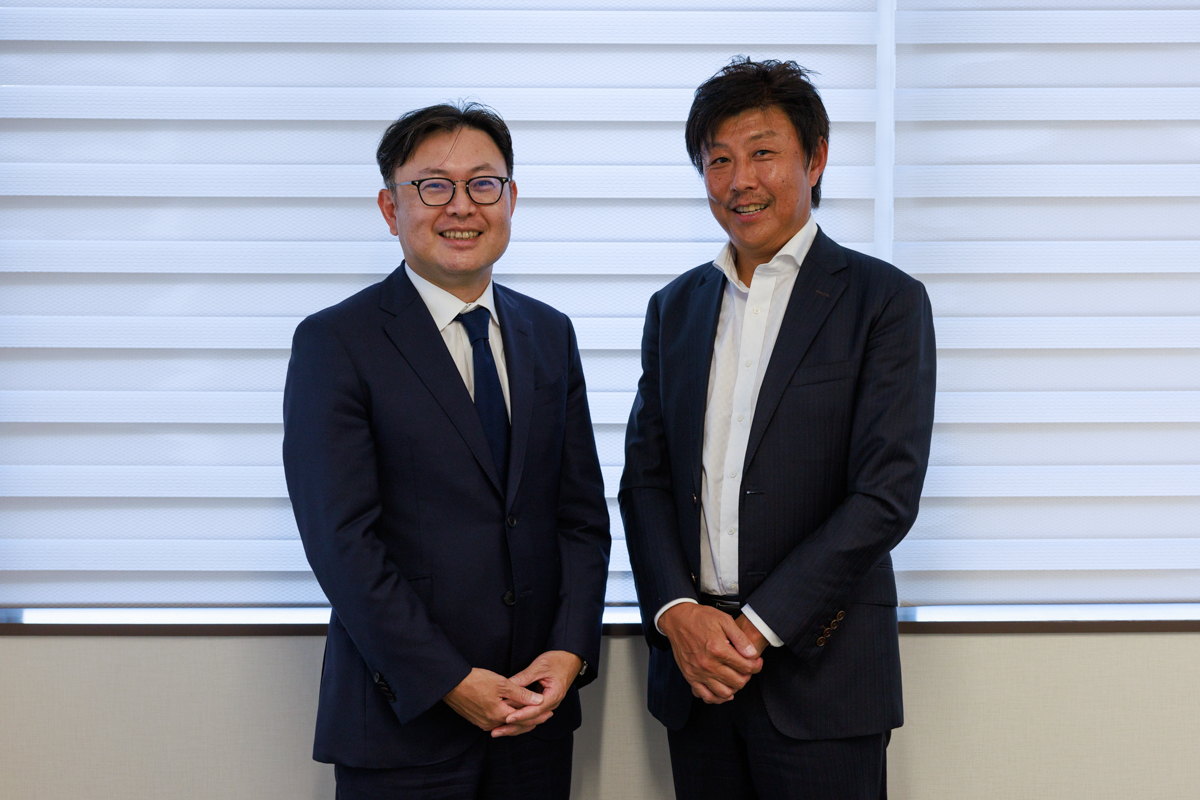ローカルM&Aマガジン
事業承継ファンドとは、中小企業の事業承継をサポートするために組成されたファンドです。ファンドによる事業承継について、その仕組みとメリット・デメリットを解説しましょう。
事業承継ファンドとは?

「ファンド」というと、「ハゲタカファンド」のような言葉の悪いイメージが先行してしまう経営者も多いかもしれません。
正しく理解するために、まずは事業承継ファンドの概要と仕組みについて説明しましょう。
ファンドとは企業に出資するための「基金」
ファンドとは、「資金・基金」という意味です。
ファンドは投資家から集められたお金によって組成され、集まったお金をファンドマネージャーが投資し、得た収益を投資家に再分配します。
ファンドには、集めた資金を上場企業株式に投資するヘッジファンド、非上場株式に投資するプライベート・エクイティファンド、不動産に投資する不動産ファンドなど、さまざまな種類が存在します。
事業承継ファンドとは、中小企業の株式を買い取り、株価を上げて転売したり上場させたりして、投資家に収益を還元するファンドのことを指します。
買収によって事業承継を実行する
事業承継ファンドによる株式の買い取りとは、わかりやすくいえば買収です。
経営者にとって、「ファンドによる事業承継」とは、一般事業会社ではなくファンドに会社を譲渡し、新しいオーナーになってもらうことを意味します。
つまり、ファンドを活用した事業承継は何も特別なスキームではなく、経営者からすれば単に、M&Aによる事業引き継ぎの相手がファンドになるだけだといえます。
ファンドによる事業承継のメリット

ファンドに株式を買い取ってもらって事業を引き継ぐ方式は、経営者と会社にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリット①持株をすぐに現金化できる
通常のM&A同様、ファンドによる事業承継を行なった場合、株主には株価に応じた売却代金が入ります。事業承継によってオーナー経営者個人が現金を得られるのは、大きなメリットといえるでしょう。
ただ、オーナー企業の場合は経営者が株式の大半を保有しているケースが多く、株式の売却金額は時に多額にのぼります。
売却後に重い税金が課される可能性があることには、充分注意しましょう。
メリット②後継者問題を解決できる
ファンドによる事業承継の場合、ファンドの人員が後継社長を務めるわけではなく、外部からプロ経営者を連れてきて雇用するパターンが一般的です。
ファンドの人員は、CEOなどといった立ち位置で、複数の投資先を掛け持ちしながら承継後の企業運営に携わることになります。
したがって、後継者不足に悩んでいた企業でも、ファンドによる承継であれば、後任の経営者がスムーズに決まるのです。
メリット③ファンドの資金力とノウハウを活かせる
ファンドには、さまざまな企業を買収してきた経験があり、企業価値を高めるノウハウを持っています。
さらに、ファンドは対象企業の買収後もキャッシュの余裕があり、資金調達力も高いです。
経営ノウハウと豊富な資金力により、承継後の業績を大きく伸ばしてくれるかもしれません。
ファンドによる事業承継のデメリット

一方で、ファンドを活用した事業承継のデメリットとはなんでしょうか。
デメリット①短期間で転売されるリスクがある
ファンドはあくまでも、Exit(イグジット、出口戦略)を目的として投資を行ないます。
つまり、購入金額より高く株式が売れればファンドとしての目的は達成されるので、状況によっては短期の保有でファンドが株式を売ってしまう可能性があるのです。
逆に、思ったような企業価値向上が実現できないと判断されれば、「損切り」として転売される場合もありえます。
デメリット②企業価値偏重の経営をされる
繰り返しますが、ファンドの投資目的は保有する株価の向上です。
目的達成のため、コスト削減をはじめとする、従業員に痛みをもたらす改革が断行される可能性は、充分に考えられます。
ファンドの利益のために無理な上場計画を推し進めて失敗するのも、よくあるケースです。
最悪の場合は、散々リストラされて価値のある資産だけになった状態で、会社が切り売りされてしまうかもしれません。
デメリット③企業文化に合わない経営をされる可能性がある
ファンドの経営手法とは、高度な財務管理や経営理論に基づくもので、承継前にワンマン社長がカリスマで組織を率いていた企業の場合、経営の方向性に大きなギャップが生じます。
ファンドの経営ノウハウによってスムーズに成果が出れば良いのですが、文化の違いが要因で従業員のモチベーションが急激に下がったり、大量離職を招いたりする懸念もあるのです。
まとめ
一口に事業承継ファンドといっても、それぞれのファンドの方針や担当者の個性によって、承継後に会社がどうなるのかは、180度変わります。
ファンドを活用した事業承継を考えるのであれば、引き継ぎ後の自社に明るい未来をもたらしてくれる相手を、慎重に選びましょう。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役