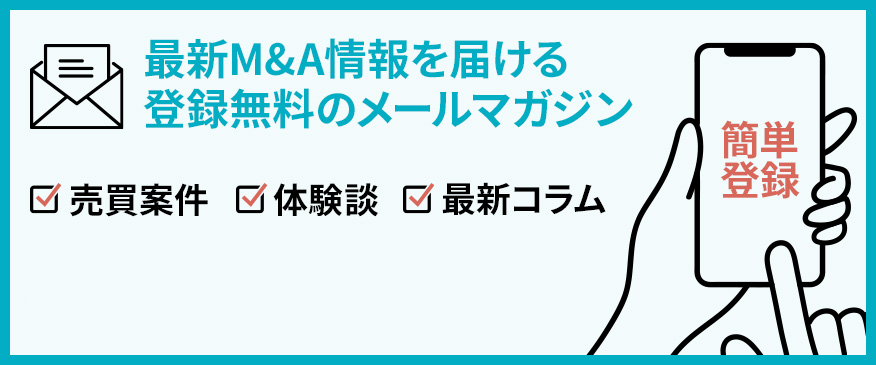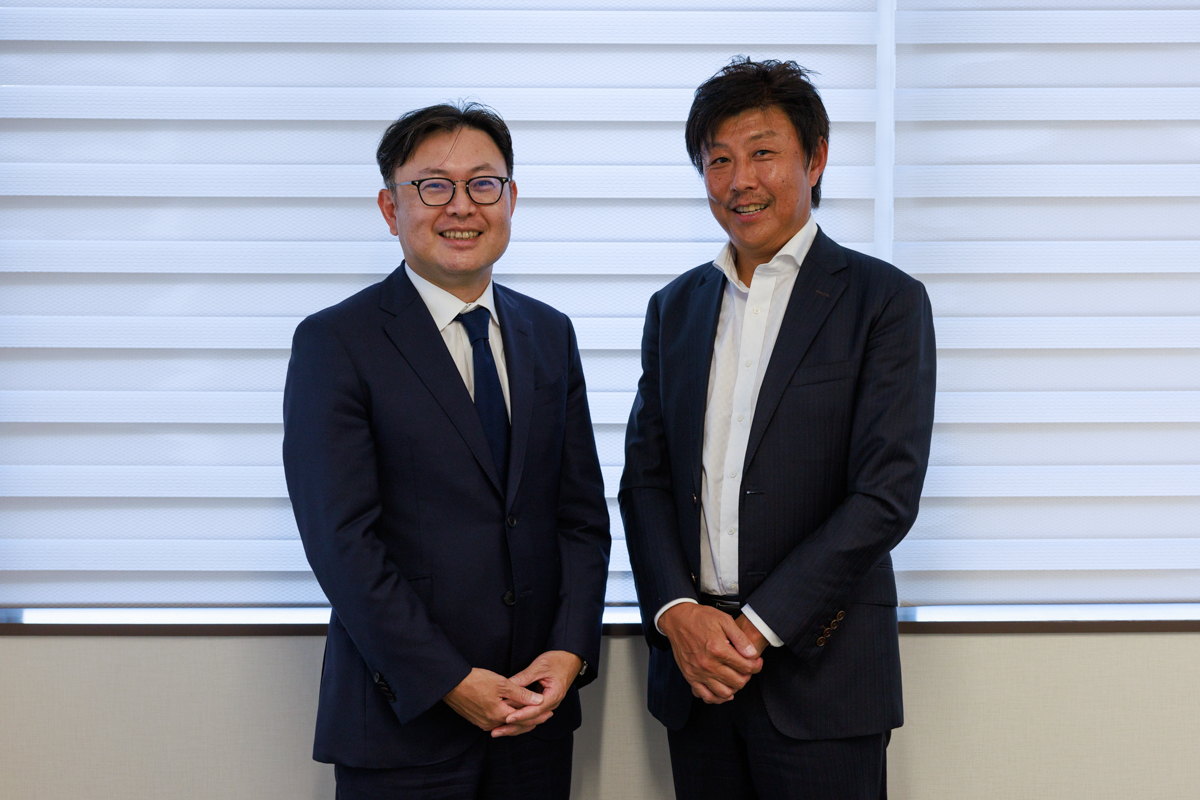ローカルM&Aマガジン
その中で気づいたのは、事業承継が失敗してしまうケースには、一定の共通点やよく見られるパターンがあることです。
事業引継ぎが失敗してしまう会社の「あるある」を紹介しましょう。
あるある①引退した前経営者が口出しする

前社長が存命のまま事業承継を行った場合、当然ながら経営の実権は後継社長が握って前社長は一線から退くことになります。
ただ、後継社長に事業を引き継いだ後も、つい口を出してしまう前社長が少なくないのです。前社長がバリバリのワンマン社長であったり、事業承継後も会長として役職を持ち続けていたりするような場合によく見られます。
前社長の口出しで後継社長を振り回せば、後継社長は経営者として力を発揮するチャンスを失ってしまいます。加えて、従業員からも「結局実権は前社長が握っているんだ」と見なされ、ガバナンスが混乱してしまうのです。
前社長は後継社長に相談されたらアドバイスする程度にとどめ、口出しをしたくなっても極力我慢したほうがいいでしょう。
あるある②準備不足で社内が混乱する

事業承継の際、準備らしい準備や引き継ぎなしに、「来期から息子に任せる」などとだけ決めたまま承継を実行に移してしまうケースは、けっこう多いもの。前社長が天才肌の営業マン出身だったり職人気質だったりする企業の場合に顕著で、そもそも経営のノウハウや業務内容を言語化することが苦手なのです。
そういった経営者は「ぶっつけ本番で叩き上げる以外に成長の道はない」という考えを持っていることも多いですから、結果として引き継ぎ不足につながります。
しかし、経営者が自覚しているかどうかにかかわらず、会社とはシステマティックに動いているものです。システムを理解しないままいきなり後継者が社長になっても、すぐ的確に動ける人はあまり多くありません。
結果、会社が承継前のように回っていかず大混乱になり、取引を失ったり従業員が大量離職してしまったりするパターンがしばしば見られます。
あるある③既存従業員からの反発
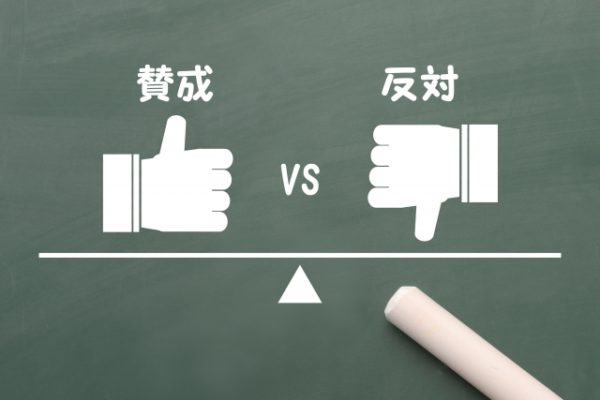
「番頭」と言われるような現場のトップや古参の従業員は、自分の業務にプロとしてプライドを持っています。大学を卒業して別の会社で働いていた社長の息子が後継社長として入社してくるのは、内心面白くない、という従業員も多いのです。
特に番頭の場合は「本当に後継者にふさわしいのは自分だ」と思ったとしても仕方のないところでしょう。
まずいのは、「後継社長派」と「反後継社長派」のように社内が二分され、争いになってしまうケース。内紛を抱えていれば当然ながら業務の効率は下がりますし、どちらかの派閥の従業員が大量離職してしまうリスクもあります。
後継社長としても、経営どころではない段階の問題を抱えることになってしまうのです。
あるある④株式の分散
事業承継を機に、今までは自分だけが持っていた株式を創業家一族や幹部社員に配分しよう、と考えるオーナー社長もいます。
しかし、軽はずみに判断してはいけません。株式の分散は、中小企業の経営において大きなリスクになりえます。
会社法上、持株比率は会社に対する影響力そのもの。たとえ一株でも持っていれば、株主として発言力が生まれます。
特に、複数の人間が結託すれば持株比率が3割以上になるケースや、後継社長の持株比率が過半数を超えていない場合などは要注意で、後継社長の決定を他の株主が否認したり、クーデターを起こしたり、投資家に勝手に会社を売却したりすることができてしまうのです。
上場企業のような大企業でも、株式の分散にまつわるトラブルはしばしば起きています。
中小企業であれば特に、事業承継後の株式は後継社長に集中させるほうがいいでしょう。逆に、承継前の株式保有者が散っているのであれば、承継を機にまとめておいたほうがいいかもしれません。
まとめ
事業引き継ぎの失敗例について、代表的な4つのケースを紹介しました。
これらの失敗が起きてしまう背景には、事業承継に関する経営者の知識不足がある場合が少なくありません。
司法書士さんに株式の承継の実務をお願いすることが多いと思いますが、全体的な影響がどうなるのかという観点で弁護士や我々のようなコンサルに相談すると後々のトラブルは避けられることが多いです。
正しい知識を身につけ、事業承継を成功させましょう。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役