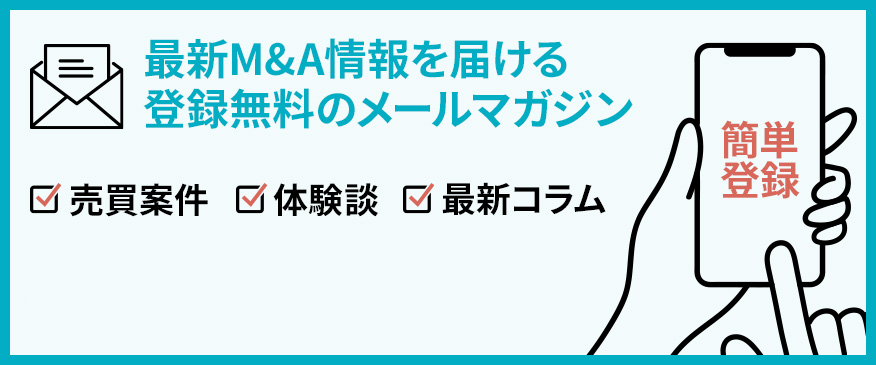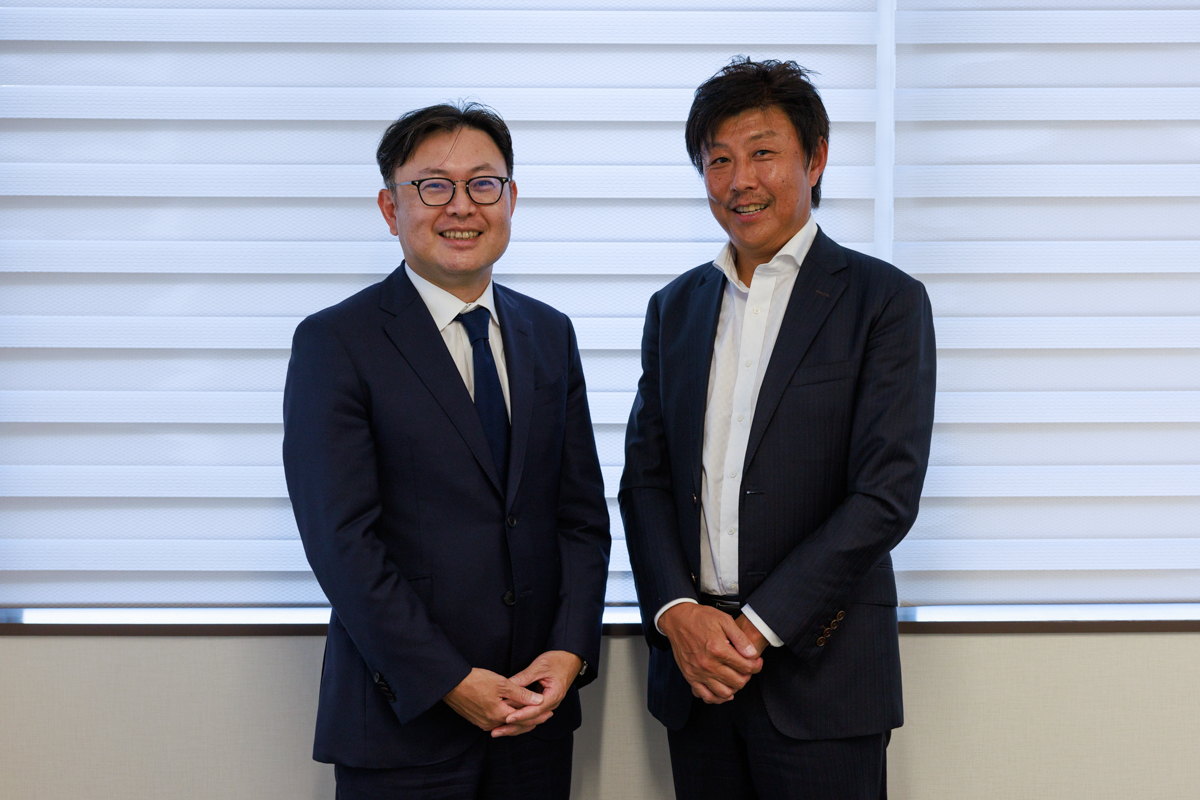ローカルM&Aマガジン
M&Aが実行され始めた1980年代には大企業が海外企業を買収するイメージでしたが、近年では中小企業のM&Aも活発化しています。
今回の記事では、中小企業のM&A事情を、新潟県の状況も踏まえながら解説します。
中小企業のM&A相談が増えている!

近年のM&Aの傾向として、小さな会社からの売却の相談が増えています。ここでいう小さな会社とは、主に年商1億円以下のファミリー企業のことを指します。
経済産業省は、2019年12月に「第三者承継支援総合パッケージ」を策定し、今後10年間で第三者承継、つまりM&Aを60万件にする目標を掲げました。
このパッケージの選定基準は、黒字廃業の可能性があり、かつ2025年までに70歳以上になる後継者不在の中小企業。約127万社のうち、60万社が該当します。
このような施策により、中小企業のM&Aも浸透してきたということがわかります。
M&Aの多い業界は?
新潟県のM&Aでとくに多い業界は、自動車業界と建設業界です。それぞれの特徴をみていきましょう。
自動車業界のM&Aの特徴

自動車業界のなかでもM&Aが活発化しているのは、自動車整備工場やガソリンスタンドを展開する企業などです。
ただし、「売りたい」と手をあげる企業は多いものの、財務内容や立地や将来性がネックになることが多いようです。
たとえば、自動車整備工場は認証工場と指定工場の2種類あります。
認証工場は地方運輸局長から認証を受け、自動車の分解整備ができます。 ただし、認証工場は車検の検査を車検場で受けなければなりません。
指定工場は工場内で車検を取ることができ、民間車検場とも呼ばれます。車検を自社で完結するのが、指定工場です。
検査場へ持っていかないと車検が通らないのが、認証工場です。
指定工場は中古自動車の販売業やガソリンスタンドなどからニーズは高いです。しかし、認証工場は指定工場よりもニーズは少ないですが、自動車整備士2級の保持する社員の年齢が若かったり、財務内容が良ければ引き合いもあるようです。
ガソリンスタンドの場合は、カーボンニュートラル宣言により今後ガソリン車がなくなる恐れがあるため、たとえ会社を手に入れたとしても、将来的に不安要素が残ります。とはいいつつも立地やこれも財務内容により、マッチングの可能性はあります。
このような理由から、これらの事業は自分の代で廃業したほうがいいと考える経営者も少なくありませんが、後継社長が業績を伸ばせる見込みがあるなら、購入するメリットは十分にあります。
たとえば整備工場なら、顧客の数です。そのなかでも法人と個人の割合、付随する、損害保険の契約数などが隠れた魅力となるようです。また、技術者の腕の良さや、あと何年勤続できるかなどの将来性が評価されていれば、相乗効果が期待され、企業価値は高いといえます。
建設業界のM&Aの特徴

新潟県には建設業の事業所が多いです。総務省統計局のデータによると、2021年12月時点で新潟県の建設事業所数は5180件で全国7位。人口10万人あたりの事業所数は235件で、全国4位となっています。
新潟県は土地柄、豪雨や豪雪、地震といった自然災害が多い地域で、「災害に強い男」の異名を持つ田中角栄氏の出身地でもあり、1988年に猛威を振るった羽越豪雨では、田中氏がリーダーとして復旧および復興に貢献して建設業に勢いをつけました。
かつては元気だった建設業ですが、今後大きな成長を遂げる可能性は低く、そのため、価値が高いうちに売却してしまおうと考える経営者が増えています。
今後活発とみられる業界は?

ほかにもM&Aで注目していきたい業界は、流通・小売業です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、スーパーなどの小売業は大きく売上を落としました。
コロナ禍のピークよりは売上高が戻ってきている事業者もありますが、全国各地でイオン系列など大手のスーパーが増加していることもあり、地方のローカルスーパーが生き残っていくのはかなり厳しいと思われます。
とくに店舗の出店への投資を重ねているのであれば、その店舗の設備更新の負担が将来の負債となる可能性があります。さらに最近は資源高による、冷暖房費の増加、食品トレーなどの容器代の増加など運営コストの増加も経営を難しくしているようです。
また、ドラッグストアのような小売事業も、陣取り合戦のように場所や顧客の取り合いが激化して、長期的に生き残っていくのは難しいかもしれません。
さらに高齢化が進み、体が思うように動かない高齢者が増えれば、小売業の集客はさらに苦しくなっていきます。
このような事情を鑑みて、M&Aによる業界再編は必須であるといえるでしょう。
まとめ
M&Aの売り手側は自分の業界事情を認識しておかなければ、いざというときに廃業を選ぶことになります。
一方で買収側としては、厳しい業界で安定した経営を続けてきた会社をM&Aする大きなチャンスが訪れています。
いずれにしても、自分の将来を考慮して最良の選択を心がけましょう。

小川 潤也
株式会社絆コーポレーション
代表取締役